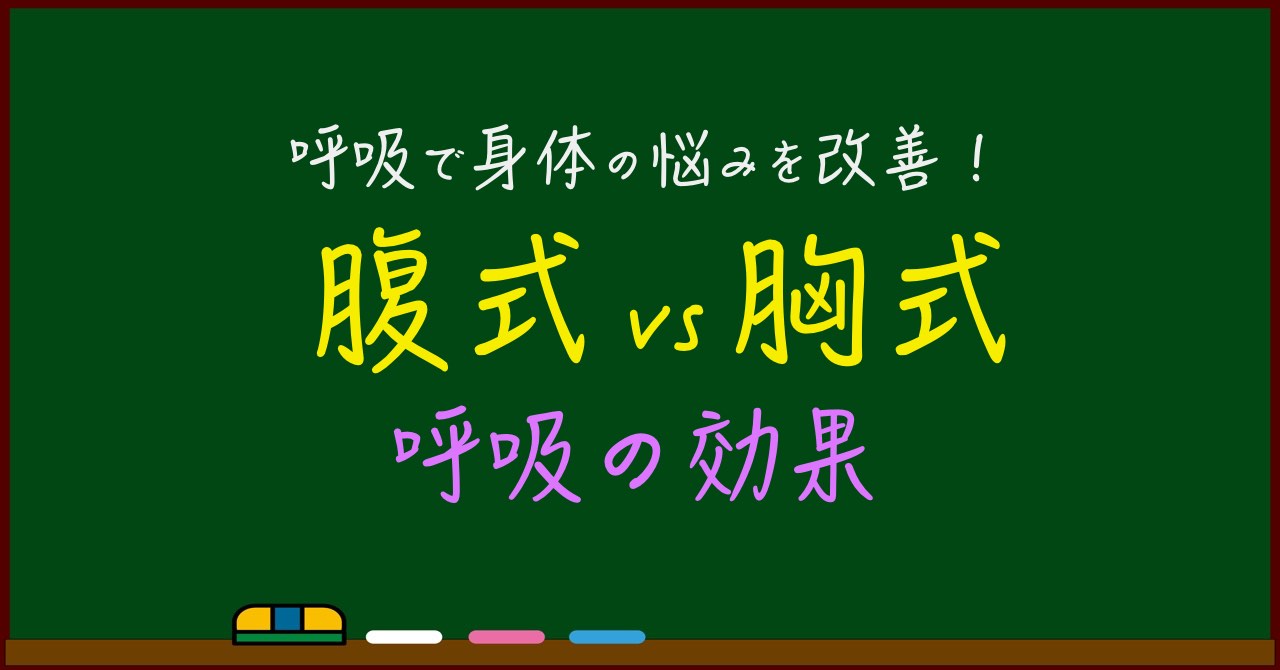【ストレッチ】の種類、怪我を予防しながら柔軟性向上効果を高めるための基礎知識(解剖学と生理学)、目的に応じた正しい【ストレッチ】のやり方についてまとめました。
ストレッチとは?
「ストレッチ」は、一般的に柔軟性を高めて関節の可動域や柔軟性を高める目的で行うアプローチの総称で、筋肉を一時的に「伸張させる」手段を使います。
柔軟性には様々な要素が関連しますが、ストレッチの主なアプローチ対象は筋トレと同じ骨格筋で、血行促進や疲労回復効果もあるため他のトレーニングの前後に行うウォーミングアップやクールダウンにも組み込まれます。
不良姿勢や日常の癖などが原因で筋肉が短縮したり硬い状態(柔軟性低下)になっていると姿勢やアライメントが崩れて、運動パフォーマンスが低下してしまいますし、怪我や肉離れなどの原因にもなってしまいます。
ストレッチによって筋肉や関節の結合組織の柔軟性を向上することにより、全身の筋肉バランスが整うことで、様々な健康効果、美容時効果、ボディメイク効果が期待できます。
正しい【ストレッチ】メリットと効果
【ストレッチ】は、「ウォーミングアップ」「クールダウン」「柔軟性を高めるためトレーニング」として取り入れられることが多いですが、目的を達成するために効果的な「ストレッチ」の種類を選んで正しいやり方で実践できていますか?
【ストレッチ】=「柔軟性アップ(身体を柔らかくする)トレーニングやエクササイズ」と漠然と捉えている人がほとんどだと思いますが、【ストレッチ】は、関節構造と関節を支える周辺組織(筋肉や筋膜な)に対してアプローチするトレーニング手法なので、目的にあった正しいストレッチ法を選んで正しく実践すれば様々な効果が期待できます。
- 筋力強化
- 動きの習得能力改善
- パフォーマンス改善
- 心身のリラックス
- 身体の変化へ意識が向くようになる
- 怪我(筋肉・関節・腱などの損傷)リスク低下
- 筋肉痛緩和
- 筋肉の緊張緩和
- 関節の結合組織(潤滑成分)の増加
【ストレッチ】よくある間違いと勘違い
【ストレッチ】を効果的に取り入れると、「柔軟性(関節可動域)向上」だけでなく様々な効果が期待できますが、必要なときに適切なストレッチ方法を選んで正しく実践できている人はあまりいません。
- 目的に合わないストレッチの種類を選んでいる
- ストレッチ間に十分な休息を入れていない
- オーバーストレッチ(負荷や回数が多いほど効果的だと思っている)
- 間違った方法でストレッチをしている
- 間違った順序でストレッチをしている
なんとなく【ストレッチ】の形(ポーズ)を真似しているだけでは、本当の意味での【ストレッチ】効果やメリットは実感できず、逆に関節や筋肉を痛めて怪我や関節障害リスクを増強させてしまいます。
どんなトレーニングにも共通していますが、【ストレッチ】も正しい方法(手段)を選んで、正しい手順で実践しなければ、効果は期待できません。
そもそもなんとなくやっていたら、間違っているのか正しいのかも判断できませんので、【ストレッチ】の目的や効果、正しいやり方を整理しましょう。
【ストレッチ】種類と正しいやり方
【ストレッチ】は大きく「動的ストレッチ(動きを伴うストレッチ)」と「静的ストレッチ(動きを伴わないストレッチ)」の2種類に分けられ、動的ストレッチは「動的柔軟性」を高め、静的ストレッチは「静的柔軟性」を高める効果があります。
| 名称 | 方法 | 補足 |
|---|---|---|
| バリスティックストレッチ | 反動をつけた反復運動で可動域を超えて筋肉を伸張する | 伸張反射が起きやすい (柔軟性向上効果はない) |
| ダイナミックストレッチ | 可動域範囲内でゆっくりと手足を振ったり身体をねじる動きや体操の中で可動域範囲内で筋肉を伸張する | 動的柔軟性向上効果あり ラジオ体操1のような運動 ウォームアップに最適 |
| スタティックストレッチ | 筋肉が最大長になるような姿勢を維持 筋肉の伸張反射を抑制しながらゆっくり可動域を広げる方法 | 可動域拡大を目的とした静的ストレッチの基本 |
| アイソメトリックストレッチ | 筋長(関節可動域)を変えず、抵抗を加えて筋肉を収縮させることで可動域を広げる方法 スタティックストレッチ手法のひとつ | 柔軟性向上効果が高いが負荷も大きいため制限あり |
| パッシブストレッチ | 可動域範囲内で、補助付きで姿勢を保持(維持)する スタティックストレッチ手法のひとつ | リラックスストレッチ 疲労回復を目的とした「クールダウン」向き |
| アクティブストレッチ | ポーズや姿勢を自力で維持することで主動作筋を強化しながら関節可動域を拡大する方法 | ヨガポーズなど空間で姿勢を維持する能力を高めるストレッチ方法 |
| PNF 固有受容性神経筋促進 | アイソメトリックストレッチ直後にストレッチを追加新しい可動域を受容器に学習させる方法 | 神経筋を促通するリハビリ手技のひとつ 柔軟性拡大と筋力増強強化が最も高い |
一般的に、「動的ストレッチ」は「ウォーミングアップ」向きで、「静的ストレッチ」は「クールダウン」や「柔軟性(関節可動域)向上目的のエクササイズ」に適しています。
【ストレッチ】方法(最適な保持時間など)目的、個人の状態、環境などにより異なるのですが、10秒から1分(または数分)程度が目安となります。
単独の筋肉(筋肉群)にアプローチできるのではあれば成人で20秒程度、成長期の子供で約7〜10秒の保持で十分で、ストレッチ後には十分な休息時間をとることも大切です。
【バリスティックストレッチ】
【バリスティックストレッチ】は、「ダイナミックストレッチ(動的ストレッチ)」のひとつで、体幹や四肢の動きに反動をつけて、可動域以上に動かすトレーニングです。
【バリスティックストレッチ】に「関節可動域を広げる(柔軟性を高める)効果」やリラックス効果はなく、むしろ「伸張反射」で筋肉が短縮しやすくなるので、解剖学構造を理解せずに行うと関節を保護するための組織の損傷や怪我につながります。
【ダイナミックストレッチ】
【ダイナミックストレッチ】とは、一般的に「動的ストレッチ」と呼ばれるトレーニング方法です。
可動域範囲で腕や脚を振り子のように使ったり、体幹をねじるようなゆっくりとした動きを使いながら筋肉と関節を伸ばす「ラジオ体操第一」のように、身体を動かしながら徐々に可動範囲やスピードを増加させていくストレッチ方法です。
同じ「動的ストレッチ」分類される「バリスティックストレッチ」との違いは、可動域の範囲を越えるための反復や身体の硬さ(筋肉や筋膜の抵抗)を実感するような無理な動作を含まない(現在の関節可動域を超えないように身体を動かす)ことです。
【ダイナミックストレッチ】は動的柔軟性を向上させる効果があるので、有酸素運動や負荷の大きい運動を行う前の「ウォーミングアップ」として最適なストレッチ方法です。
【ダイナミックストレッチ】は、8〜12回の繰り返しを1セットとすることで効果が高まりますが、筋肉が疲労するとせっかく伸ばした筋肉の神経制御がリセットされてしまって関節可動域が拡大しないので、これから行う運動の可動域を高める目的を忘れず、疲れないように行うことが重要です。
【スタティックアクティブストレッチ】
【スタティックアクティブストレッチ】は【アクティブストレッチ】と呼ばれることもありますが、ヨガポーズなど特定の姿勢を補助なく維持しながら筋肉を伸張させるトレーニング方法です。
【スタティックアクティブストレッチ】は、ターゲットとなる筋肉を筋力強化しながら動的な柔軟性を高める効果がありますが、負荷が大きいので長時間やる必要はありません。(10秒程度保持が目安)
【パッシブストレッチ】
【パッシブストレッチ】とは、「リラックスストレッチ」や「スタティックパッシブストレッチ」などとも呼ばれ、身体の他の部分やパートナーの補助などを使って姿勢を保持するトレーニング方法です。
例えば、立って片脚を身体の前面に高く上げた状態を補助なしで維持する場合は、ハムストリングの「スタティックアクティブストレッチ」ですが、仰向けに寝て(床に支えてもらい)手で補助して片脚を上げ場合は、ハムストリングの【パッシブストレッチ】になります。
【パッシブストレッチ】はゆっくりとリラックスして行うストレッチなどなので、損傷後のリハビリや運動で疲労した筋肉を癒す「クールダウン」として最適です。
各ストレッチの間に15〜30秒の休憩を入れて、2〜5回程度の繰り返しが目安です。
【スタティックストレッチ】
【スタティックストレッチ】は、ターゲットとなる筋肉(筋肉群)が最大長になる姿勢を保持しながら静的柔軟性(可動域拡大)を目指すトレーニング方法で、静的ストレッチの基本形です。
【スタティックストレッチ】は「パッシブストレッチ」と混同されがちですが、リラックスした状態で外力を活用して関節を可動させる「パッシブストレッチ」は、【スタティックストレッチ】の特別形です。
【アイソメトリックストレッチ】
【アイソメトリックストレッチ】も「スタティックストレッチ」手法のひとつで、自分の身体、壁や床などを活用したり、パートナー(トレーナー)の協力で抵抗を加え、同尺性収縮で筋肉を最大長に伸張させるトレーニング方法です。
【アイソメトリックストレッチ】は、「パッシブストレッチ」と「アクティブストレッチ」のいいとこどりをしたような方法で、「パッシブストレッチ」で伸張された筋肉に更に抵抗を加えて「同尺性収縮」させます。
【アイソメトリックストレッチ】では、「伸張反射」を抑制しながら伸張された筋肉の長さを「筋紡錘」に一定期間記憶させることができますので、ストレッチの悩みである伸張痛を大幅に軽減しながら柔軟性維持効果が高いことが特徴です。
もちろん、「ストレッチ」をやめると筋繊維はいったん静止長に戻りますが、「ストレッチ」された筋長を「筋紡錘」が記憶しているので、その範囲までなら伸張反射が起こりにくくなっている(パッシブストレッチの伸張反射を超えてストレッチされた筋肉が収縮するのを抑制)ので、可動域が拡大して柔軟性が向上していることを実感できます。
「ストレッチ」などで筋肉が収縮する際、必ずしも全ての筋繊維が収縮するわけではないのですが、抵抗を使うことで筋肉の両端が引っ張られてより多くの筋繊維が収縮に参加することになり、より多くの筋繊維が関与していることも柔軟性改善効果が高い理由です。
【アイソメトリックストレッチ】基本のやり方は、姿勢を固定したあと抵抗を加えて7-15秒ほど保持し、20秒以上リラックスさせます。
【アイソメトリックストレッチ】は、効果が高い分負荷が大きいので、成長期の子供やすでに十分な柔軟性がある人に行うと、関節を保護するための組織である腱や結合組織を伸ばしすぎて損傷するリスクが高まり危険なので避けましょう。
また、【アイソメトリックストレッチ】を行う前にターゲットマッスルの動的筋力トレーニングをしておく(筋肉の作用を身体で理解しておく)こと、また36時間に1回を限度とすることも重要な注意事項です。
【PNFストレッチ】
【PNFストレッチ】とは、「パッシブストレッチ」と「アイソメトリックストレッチ」のメリットを合わせたような方法で、「静的柔軟性」を最大限高める効果が期待できます。
PNFとは、「Proprioceptive Neuromuscular Facilitation」の略で、日本語では「固有受容性神経筋促進法」と訳されていて、もともとは脳卒中のリハビリ手段として開発されました。
【PNFストレッチ】は、受動的にストレッチされた筋肉を抵抗に対して同尺性収縮(アイソメトリックストレッチ)させた後に、拡大した可動域で再度パッシブストレッチをする方法です。
「アイソメトリックストレッチ」後に「筋紡錘受容体」に伸びた筋長が記憶され、かつ「伸長反射」による筋肉収縮が抑制され、かつ、疲労した速筋繊維がその後のストレッチで抵抗しにくくなっている状態を活用して、更に受容体を刺激して拡大した可動域を定着させていくことを狙った方法です。
【PNFストレッチ】にはいくつかの方法がありますが、最も一般的なのは「同尺性収縮」と「弛緩」を繰り返す「hold-relax(ホールドアンドリラックス法:contract-relaxとも呼ばれる)」で、1サイクルが以下の3つのステップになります。
- 「パッシブストレッチ」した筋肉を7-15秒「アイソメトリックストレッチ」
- 2-3秒リラックスしたらすぐに最初よりも可動域を拡大させて「パッシブストレッチ」をして10-15秒保持
- その後20秒以上リラックスして休憩
2回目の「パッシブストレッチ」を「アイソメトリックストレッチ」に変えた「hold-relax-contract(contract-relax-contract/contract-relax-antagonist-contract)」法もあります。
これは最後のステップを「逆制止による拮抗筋収縮」に置き換えているため、最初のパッシブストレッチを受けた筋肉をリラックスさせて更にストレッチする効果とパッシブストレッチで筋肉組織を痛めるリスクを軽減できます。
また、「アイソメトリックストレッチ」に「パッシブストレッチ」を加えて更に柔軟性を高める手法もありますが、怪我をするリスクも高くなるので注意が必要です。
他にも、2回目の「パッシブストレッチ」を「ダイナミックストレッチ」や「バリスティックストレッチ」に変えた「hold-relax-swing(hold-relax-bounce)法」もありますが、これは高いレベルのスポーツ選手など筋肉のストレッチ反射を適切にコントロールできる訓練をしていない人が行うと関節を痛める危険性が高いので基本的には避けるべき手法です。
もちろん、「アイソメトリックストレッチ」を含む【PNFストレッチ】は、成長期の子供にも不適切なストレッチ方法です。
【PNFストレッチ】は「アイソメトリックストレッチ」同様に受動的及び能動的な柔軟性向上と筋力強化に効果的ですが、その分負荷も大きいので、ひとつの筋肉群に対してひとつのテクニックのみ 1〜5サイクル程度までとし、次のセッションまで36時間程度は空けるようにしましょう。
ひとつの筋肉群に対して1回だけやるのと3〜5回程度やるのでは、効果に大きな違いがないという研究もありますので、関節に負荷をかけすぎないように丁寧に行いましょう。
【ストレッチ】効果を高める3つのコツ
効果的な【ストレッチ】を選んで正しく行うためには、ストレッチのターゲットとなる関節の解剖学構造とストレッチによる身体の変化(生理学)を理解しておく必要があります。
その上で、以下の3つの要素を意識して、目的に合わせた「ストレッチ」を正しく実践しましょう。
- アイソレーション(隔離)
- レバレッジ
- リスク
アイソレーション(隔離)
一般的に一度に【ストレッチ】する筋肉の数が少なければ少ないほど効果を高めることができますので、一番効果的にかつ完璧に特定の筋肉(筋肉群)を【ストレッチ】するには、その筋肉(筋肉群)を他の筋肉から完全に切り離す必要があります。
他の筋肉の代償や拮抗(抵抗)を気にしなくてよければ、誰でも確実に【ストレッチ】したい筋肉を効果的に【ストレッチ】できますが、私たちの身体の筋肉は「筋膜」を介して相乗作用する筋肉や拮抗する筋肉ともつながっていて、特定の筋肉だけにアプローチすることはできません。
ただ、効果的な【ストレッチ】をするために、できるだけ関与する筋肉(筋肉群)を少なくなるように姿勢や方法を工夫することはできます。
例えば、座り姿勢で短縮しがちな両脚裏の「ハムストリング」も、両脚同時に伸ばそうとするよりも片脚ずつ行う方が抵抗を制御しやすくなるので【ストレッチ】効果をより高められます。
また、「協力筋」を先にストレッチしておくことで、ターゲットマッスルをストレッチするときの制限要因にならないため(実質的に隔離できる)、より効果的にターゲットマッスルを【ストレッチ】できます。
逆を言えば、複数の筋肉群を同時にストレッチしようとすればするほど抵抗も増えて難易度が高く(コントロールが難しく)なります。
例えば、「開脚」はストレッチで柔軟性を高めたい人の憧れのポーズですが、両脚を同時にかつ複数の筋肉群を同時にストレッチしようとしているため難易度が高いのです。
レバレッジ
【ストレッチにおけるレバレッジ】とは、強度や速度を適切にコントロールすることです。
具体的には、運動学的なつながりを意識して【ストレッチ】する順番を考えることなどが効果的で、基本的には以下の順番が効果的です。
- 背中をストレッチする
- 背中をストレッチした後に脇腹をストレッチする
- お尻をストレッチした後にハムストリングをストレッチする
- ふくらはぎをストレッチした後にハムストリングをストレッチする
- スネのストレッチをした後に大腿四頭筋をストレッチする
- 腕のストレッチをした後に胸のストレッチをする
最大効率で筋肉にアプローチすることで怪我や痛みを予防しながら最大限の効果が期待できますし、正しくレバレッジを効かせることができれば大きな力を使わずに適切な強度で最も効果的な【ストレッチ】できます。
リスク
【ストレッチ】は柔軟性を高めて疲労を回復する優れた効果がありますが、関節の動かし方や筋肉および軟部組織への負荷のかけ方を間違えると関節に負担をかけて怪我につながるリスクが常にあります。
特に、腱や靭帯に負担のかかるひねりや背骨の椎間板の圧迫などには特に注意が必要です。
十分な解剖学知識と筋力や柔軟性があるか、プロの指導下以外で行う場合以外は、期待できる効果よりもリスクの方が大きいので他の方法(軽減法や代替のストレッチ)を選択するようにしましょう。
後屈系のストレッチ
ヨガの「鋤のポーズ」や手のひらと足裏だけで全身を支えて背中で逆アーチを作る「ブリッジポーズ」など、背骨を後屈するタイプのストレッチは、不良姿勢で短縮しがちな筋肉をストレッチする効果があり、正しく行えば背骨の柔軟性を高めて姿勢改効果に優れています。
ただ、「椎間板を圧迫しやすい」「背骨や腰に負担をかけやすい」「肺と心臓を圧迫しやすい」など正しく行わないと大きなリスクと隣合わせです。
ハードル選手ストレッチ
床に座り、片脚を前に真っ直ぐ伸ばしてもう片方の脚は屈曲したまま(または両脚を屈曲したまま)身体を後ろに倒して「大腿四頭筋」を伸ばそうとするストレッチは、膝の内側側副靭帯を伸ばして半月板を圧迫するリスクが非常に高いストレッチ方法です。
膝関節のねじれや圧迫で膝蓋骨の位置がずれてしまう可能性もあります。
立位体前屈
立位で身体を股関節から折り曲げて指先をつま先や床につけようする、柔軟性を計測するときにも使われるポーズも膝や背中を痛めるリスクが高いので注意が必要です。
自分の身体をコントロールできる筋力や柔軟性が十分にない場合、膝が過進展、かつ腰椎下部を圧迫する姿勢になりがちですし、特に脚幅を広くとっているほど膝関節にも負担がかかりやすく、膝関節症など慢性的な損傷につながるリスクもあります。
ツイスト(身体のひねり)
ウエストのくびれを作る効果が高いと人気のツイスト(体幹を捻る運動)ですが、体重や反動を使って急激に大きな力で行うと背骨周りの軟部組織の段断裂を引き起こす場合がありますし、立位で行う時は、膝の靭帯にも過剰な負担をかけて損傷につながります。
逆転(逆立ち)
いわゆる逆立ちやヨガでも人気の逆転のポーズなど、頭を下にして脚を上にするポーズは、正しく負荷をコントロールして行えば高いリフレッシュ効果や姿勢改善効果が期待できます。
ただし、血圧が上昇しやすく背骨の安定性も低下するため、心臓血管系や背骨に問題がある場合は負担が大きすぎるので避けましょう。
目的別!正しい【ストレッチ】選び方とやり方
【ストレッチ】は目的に応じて、正しい方法を選んで正しいやり方で実践することで、期待する効果を実感できます。
場面や個人の身体の状態、環境など応じて最適なストレッチ方法を選びましょう。
| 目的 | ストレッチの種類 (選択例) | ポイント |
|---|---|---|
| ウォームアップ | ダイナミックストレッチ スタティックストレッチ | その後に行う運動につながる要素を組み込むと効果的 |
| クールダウン | パッシブストレッチ | 疲労回復が目的なのでリラックスして行う |
| 柔軟性(関節可動域)改善 | スタティックストレッチ | 入浴後など身体が温かくリラックスしているときに行うと効果的 |
| ボディメイク(姿勢改善) | アクティブストレッチ | 全身のバランスを整える意識を持つと効果的 |
| ダイエット(有酸素運動) | ダイナミックストレッチ | 気持ちよい伸びを感じながらストレッチ |
| リハビリ(機能改善) スポーツパフォーマンス改善 | PNF | 神経筋の伝達経路を意識 |
柔軟性を高めたい
「柔軟性」を高める目的で行う【ストレッチ】では、以下の2つの目標を達成する必要があります。
- 受容体に伸張した筋長を記憶させる
- 結合組織の抵抗を減らす
また、特定の姿勢を補助なく維持できる「能動柔軟性(Active Flexibility)」を高めたい場合は、上記に加えて姿勢を維持できる筋力も必要です。
【ストレッチ】方法を選んで実践する前に、改善したい「柔軟性」の種類やターゲットとなる関節(筋肉)を明確にしましょう。
例えば、「能動的柔軟性(Dynamic Flexibility)」を向上させたい場合は、「静的ストレッチ」と「動的ストレッチ」の組み合わせが有効ですし、「受動的柔軟性(Passive Fexibility)」向上には「PNFストレッチ」が最も効率的ですが、いずれの方法でも正しい手順と適切な負荷や時間で行います。
早く柔軟性を高めたいと無理な(過負荷や長時間の)ストレッチをすると、怪我などの原因となって、結局効果が出るまでにかかる時間も長くなってしまうので、最低でも1〜2ヶ月程度の時間をかけて徐々に柔軟性を高めて(可動域を拡大して)いきましょう。
また、柔軟性を高める【ストレッチ】は身体が温まっているときにやると効果を高められますので、身体が温まっていない場合は、「ウォームアップ」を行ってから【ストレッチ】をするようにしましょう。
更に、日内リズムで考えると、朝起きて日中活動して夜眠る生活をしている人では、2:30pm-4pmごろが最も身体の柔軟性と強度が高まっているので、朝寝起きの身体で無理をするよりも、午後や1日の終わりの入浴後で身体が温まったタイミングでストレッチする方が効果的です。
正しい方法で【ストレッチ】をすれば痛みや不快感を生じることはありませんが、もし【ストレッチ】前後に痛みや不快感を感じる場合は、すぐに中止して原因を特定します。
ほとんどの場合で負荷や姿勢が間違っています。
| 組織の問題 | 生じた要因 |
|---|---|
| 軟部組織断裂 | ウォームアップが不十分 負荷が大きい 姿勢が不適切 |
| 疲労物質の蓄積 | 負荷が大きい ウォームアップが不十分 クールダウンが不十分 |
| 筋肉の痙攣 | 急激かつ過剰な筋肉への負荷 |
原因によっては「スタティックストレッチ」や「クールダウン」を行うことで痛みや違和感が解消する場合もありますが、組織が損傷している場合は全てのトレーニングを中止し、しっかりと組織を回復させてから再開してください。
「ウォーミングアップ(ウォームアップ)」したい
【ストレッチ】=「ウォーミングアップ」と勘違いしている人も多いのですが、「ウォーミングアップ」の定義は、文字通り「warming up(深部体温を上げる」で、深部体温を1.4 〜 2.8℃程度上昇させることでスポーツなど特定の運動を行うときに動きやすい状態に整える目的に以下の手順で行います。
- ウォームアップ(深部体温をあげる)
- ストレッチ
- 目的とするスポーツやトレーニング
【ウォーミングアップ】は、深部体温をしっかりと温めた状態を作ってから「ストレッチ」をすることで、「身体への意識」「筋肉の機能(弾力性 収縮性 協調性)」「呼吸器や心臓血管系の効率性」を高め、目的としたスポーツやトレーニングで怪我をせずに最大のパフォーマンスができる準備をするために行います。
身体を資本として超人的な技やスピードに挑むアスリートやプロのダンサーでさえも、朝起きていきなり高度な技は繰り出せませんし、プロであればあるほど自分の身体と向き合って身体を目覚めさせる【ウォーミングアップ】を欠かさず、時間をかけて丁寧に行います。
また、「ウォーミングアップ」で行う「ストレッチ」は、運動習慣のない人が運動を始めようと思ったときには、最適なエクササイズになります。
運動不足を感じて「運動しないと!」といきなりスクワットや腹筋などの筋トレやマラソンなどのハードなトレーニングをやろうとしても思うように身体は動きませんし、足腰が痛くなるなど逆効果になったりしてモチベーションが続かないことがほとんどです。
私たちの身体は良くも悪くも「慣れる」ようにできています。
だから、意識して使わない筋肉は、筋肉量も脳から筋肉をつなぐ神経経路も衰えていくので、また運動ができる状態に戻すには、運動ができない人ができるようになるのと同じ位(場合によってはそれ以上)時間をかけて段階的にステップを踏んでいく必要があります。
「ウォーミングアップ」は名前の通り、身体を温めて(深部体温を上げて)身体の循環を高めることが目的ですが、筋肉や骨格(関節)に働きかけて、脳と筋肉を繋ぐ神経経路に働きかけて運動パフォーマンスを高めているので、立派なエクササイズです。
「運動不足」を実感していても、「本格的にトレーニングやエクササイズをする時間が取れない」「そこまではやりたくない」「身体がついてこない」と言う人は、「ウォーミングアップ」を習慣にすることから始めてみましょう。
気が向いたときにいつでもどこでもできるので、やる時間を決める必要はありませんし、「ウォーミングアップ」をやるだけでもだるい身体がシャッキリするので、寝起きや仕事中のリフレッシュにもおすすめです!
ウォームアップ
【ウォーミングアップ】の第1ステップは筋肉を動かすことで深部体温を上げる「ウォームアップ」で、全身の関節を全可動方向(前額面 / 矢状面 / 水平面 /円運動)に動かすダイミックストレッチをしたあとに有酸素運動を取り入れます。
最初に全身の関節を全方向に動かす理由は、これから使う身体の構造に意識を向けつつ潤滑液の作用による関節の滑らかな動きを促進するためです。
足のつま先から上に向かって、または手の指先から下に向かって筋肉(筋膜)のつながりを意識しながら、徐々に大きな関節へ向かっていくようにします。
- 指と指間
- 手首
- 肘
- 肩
- 首
- 体幹(胸や腰)
- 股
- 脚
- 膝
- 足首
- つま先
動かせる方向は関節の解剖学構造により様々ですが、ひとつひとつの関節がスムースに動くようになるまで繰り返します。
それぞれの関節が滑らかに動くようになったら、軽いランニングや縄跳びなど心拍数があがるような動き(有酸素運動)を5分以上行い、深部体温を上げながら血液循環を増加させ、筋肉のパフォーマンスと柔軟性を高めます。
ストレッチ
【ウォーミングアップ】は目的とするトレーニングやスポーツを効率的に行いパフォーマンスを高めるための準備なので、必ず「スタティックストレッチ」を行って筋肉長を整えてから軽めの「ダイナミックストレッチ」を行うという順番を守りましょう。
「ウォーミングアップ」には、「アクティブストレッチ」や「アイソメトリックストレッチ」などの筋肉に大きな負担をかけて疲労するようなストレッチは不適切です。
- スタティックストレッチ
- ダイナミックストレッチ
【ウォームアップ】後の筋肉は温かく弾力性もありますので、リラックスしたゆっくりとした動きで「スタティックストレッチ」を行います。
順番は背中から始めて、上半身、下半身と続けます。
- 背中
- 脇腹(腹斜筋)
- 首
- 前腕と手首
- 上腕三頭筋
- 胸
- お尻
- 股間(内転筋)
- 太もも(大腿四頭筋と外転筋)
- ふくらはぎ
- すね
- ハムストリング
- 足の甲
全身をくまなくストレッチするのが理想ですが、時間がない場合は、目的とする運動で使う筋肉(群)だけは必ず網羅するようにします。
「スタティックストレッチ」で筋肉長を整えたら、軽めの「ダイナミックストレッチ」を行います。
これから実際に行うスポーツ種目やトレーニングと類似する動きで最大可動域まで動かすことと、筋肉疲労を起こさない回数や負荷に止めることが重要なポイントです。
「クールダウン」したい
【ストレッチ】=「クールダウン」もよくある勘違いですが、「クールダウン」は運動後の疲労や筋肉にたまった乳酸(筋肉痛の原因)などを減らすために行うプロセスで、「ウォーミングアップ」と逆の手順で行います。
- ダイナミックストレッチ
- タティックストレッチ
理想的には運動直後に10-20 分程度の時間をかけて【クールダウン(ウォームダウン)】を実践した方がいいのですが、難しい場合は最低でも5分程度時間をとるようにしましょう。
まず最初に、心拍数が通常に戻るまで軽めに「ダイナミックストレッチ」を行ってから「スタティックストレッチ」に移行します。
この手順により、すぐに休憩するよりも血液から乳酸をスムースに排出できるため、疲労した筋肉の痙攣、こわばり、痛みを軽減して気持ちよくリラックスできます。
翌日以降も痛みや不快感が続く場合は、「ウォーミングアップ」→【クールダウン】をしましょう。
「筋トレ」と「ストレッチ」の関係
【柔軟性】と「筋力」はトレードオフの関係にあると勘違いしている人も多いのですが、【柔軟性】を高めるトレーニングと筋力増強トレーニングは連携して相乗効果を高めることができるパートナーです。
【柔軟性】を無視して筋力トレーニングはできないし、筋力を無視して【柔軟性】を高めることはできませんので、解剖学構造を理解した上で正しいストレッチ方法を選択し、目的に合わせた適切な順番で行う必要があります。
順番
基本的に、【柔軟性】を高めるトレーニングを「ストレッチ」、収縮により発生する力を強化するトレーニングを「筋トレ」とすると、特定の筋肉(群)に対する「ストレッチ」は筋トレの後に行い、筋トレした筋肉は必ず直後に「ストレッチ」することで相乗効果を高めることができます。
もちろん、「ストレッチ」をすることで筋力増強や筋肥大を制限することはありません。
例えば、ボディビルディング(筋肥大)目的のウェイトリフティング(反復動作)で疲労した筋肉は、短縮して乳酸などの疲労物質をため込んでいますので、筋肉を緩ませて短縮した筋肉に最大可動域を再度学習させながら乳酸など疲労物質を取り除く効果のある「静的ストレッチ」を直後に組み込むことで、筋肥大を更に促進して筋肉痛も軽減できます。
また、プッシュアップやサイクリングなど主要な筋力トレーニングでも最大可動域よりも小さい可動域での反復運動を繰り返すので、神経筋制御により短い筋長で記憶されて柔軟性が低下しやすくなりますので、柔軟性向上も視野に入れているのであればトレーニングにおいて常に最大可動域を意識することも重要です。
負荷
ただし、可動性と安定性はトレードオフの関係で、運動の前に関節結合組織を緩めすぎる「ストレッチ」をしてから負荷の大きい筋トレ(急激な筋収縮)をしたり、筋肉が最大長に達して更に伸ばそうとする力が加わると、伸ばしたくない(安定させることが目的の)靭帯や腱に過剰な負担がかかり、靭帯や腱断裂など怪我の原因にもなります。
筋肉自体にも関節を安定させて怪我を予防する役割がありますので、筋トレをする時には徐々に筋肉の負荷を大きくしていくことで怪我を予防しながら効果を高められます。
目的の柔軟性を獲得して1週間程度維持できるようになったら、「アイソメトリックストレッチ」や「PNFストレッチ」などの負荷の大きいストレッチは一時中断しましょう。
【ストレッチ】と呼吸
「呼吸」が浅くなると循環が低下するため、筋肉が硬くなって本来の柔軟性や筋力が発揮できなくなりますし、「呼吸」自体も、腹腔(コア)の圧力を調整する体幹筋トレかつアクティブストレッチです。
ゆっくりとした「呼吸」をするだけで、心のリラックス効果、血流改善効果、乳酸や疲労物質の除去効果もあります。
「呼吸」方法
ストレッチ中の「呼吸」は、鼻からゆっくりと息を吸い込んで胸ではなくお腹を膨らませたら、しばらく止めてからゆっくりと鼻または口から吐き出します。
鼻から吸うことで肺に入る空気の異物を取り除いて温めることができるので、できるだけ鼻呼吸を意識し、横隔膜や腹横筋を柔軟に保ったまま、肩やお腹に余計な力が入らずリラックスしていることも重要です。
「呼吸」タイミング
「筋肉」が伸びているとき(負荷をかけているとき)に息を吐くようにするとより効果的です。
「呼吸」速度調整
「呼吸」速度は喉の後ろにある声門でコントロールします。
副鼻腔で匂いを嗅ぐような吸い方ではなく、喉の内側でとても柔らかい音(hm-m-m-mn)が出るように吸い、吐くときの喉の内側から安心したため息のような音(hm-m-m-mn)が出るように吐きます。