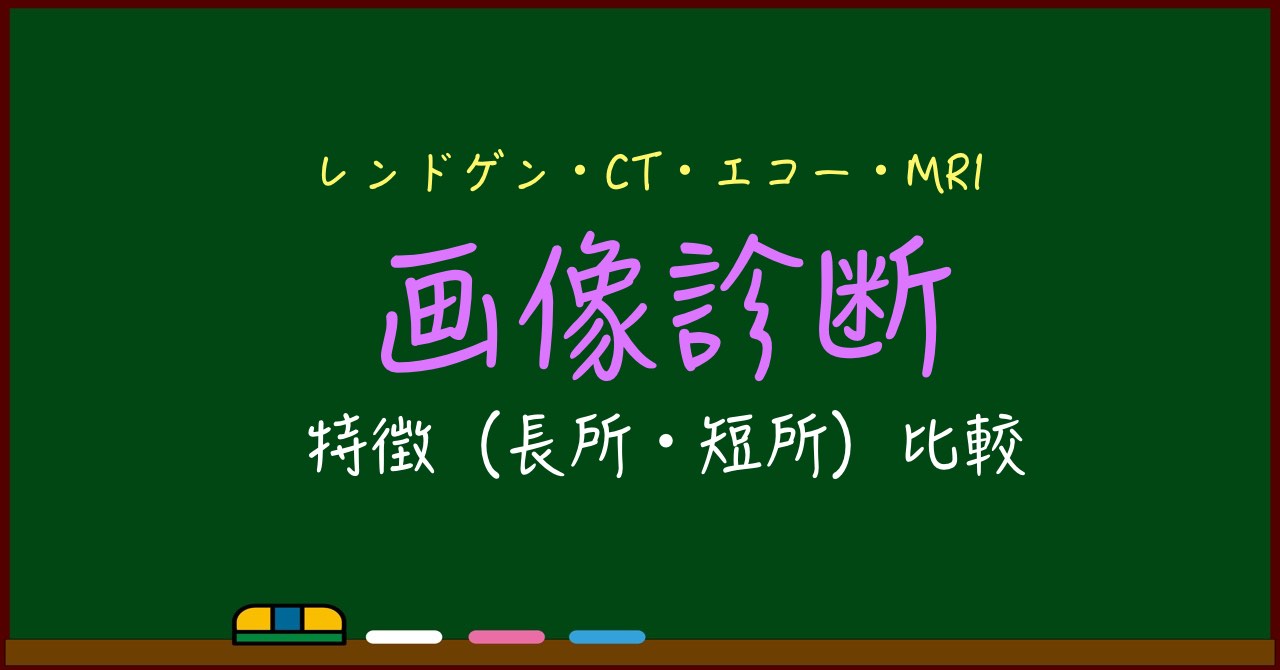【レントゲン(X線)検査】【エコー(超音波検査)】【CT(コンピューター断層撮影)】【MRI(磁気共鳴画像法)】の仕組みと特徴(長所・短所)を整理してまとめています。
画像診断の種類と特徴(長所と短所)
主要な画像診断方法である【レントゲン(X線)検査】【エコー(超音波検査)】【CT(コンピューター断層撮影)】【MRI(磁気共鳴画像法)】の仕組みや特徴(長所や短所)についてシンプルにまとめました。
| 検査の種類 | 仕組み | 長所 | 短所 |
|---|---|---|---|
| レントゲン検査 (エックス線) | X線の性質を利用 | 比較的簡単 心臓や大きな血管も映る | 形状しかわからない 放射線被ばくリスク |
| 超音波検査 (エコー) | 超音波の性質を利用 | 頭がい骨以外のほぼ全てを検査可能 断面的に見える | 内臓検査では絶食が必要 |
| CT検査 Computed Tomography | コンピューター断層撮影 | 立体的(3D)に表示できる 広範囲の検査に適している | 放射線被ばくリスク |
| MRI Magnetic Resonance Imaging | 磁気共鳴画像法 (磁石と電磁波) | 臓器や血管などの冠状断像や縦断像も撮影できる | 撮影に時間や手間がかかる |
【レントゲン(X線)検査】
【レントゲン(X線)検査】は一番古くからある画像診断で、「身体の組織のうち骨のようにX線が通り抜けにくいところほぼ白く写る」という性質を活用して画像の濃淡から体内の様子を知る事ができます。
| 項目 | 長所 | 短所 |
|---|---|---|
| 利便性 | 比較的簡単に受けられる | 形状を映し出すだけ |
| リスク | エックス線被ばくリスク | |
| 診断範囲 | 肺癌、肺炎、肺結核などでは患部が白い影として映る 心臓や大きな血管も映し出される 乳がん検診のマンモグラフィ | 癌などの診断には情報が不十分 |
【レントゲン(X線)検査】は比較的簡単に受けることができる検査なので、一次検査としてとしてよく用いられます。
【エコー(超音波検査)】特徴
【エコー(超音波検査)】は、「超音波」の性質を利用した画像診断方法です。
「超音波」は人間の耳には聞こえない高い周波数の音波で、一定方向に強く放射され直進性が高いという性質があるため、調べる部位に超音波を当ててその反響を映像化します。
組織の組成は基本的なパターンがあり、「腫瘍」「ポリープ」「炎症」「結石」などは、周囲の正常な組織と組成が異なるため、正常な組織との境界にコントラストから異常を発見できます。
| 項目 | 長所 | 短所 |
|---|---|---|
| 利便性 | レントゲンに比べて内臓の様子をより断面的に確認できる 臓器が動いている様子をリアルタイムで映せる | 腹部内に空気が多く存在すると画像が不鮮明になる(検査前絶食要) 膀胱を検査では排尿を我慢することもある |
| リスク | 放射線被ばくの心配がない 産婦人科の胎児の診察にも利用可能 | |
| 診断範囲 | 頭がい骨のように固い部分を除くほぼすべての身体部位 腫瘍などの有無だけでなく、大きさや深達度も確認できる |
【エコー(超音波検査)】では、臓器が動いている様子をリアルタイムで映し出されるため、検査のための組織を採取したり、臓器の位置を確認しながら治療を行うときに使うことも可能です。
食後は消化管内に空気が発生しやすいため消化器系の検査前は絶食が必要な場合があったり、膀胱を検査する場合は尿が溜まっている方が詳しく観察できるため、検査前の排尿は我慢して行うなど患者に負担がかかることもあります。
【CT(コンピューター断層撮影)】
CTは「Computed Tomography」の略で、日本語では「コンピューター断層撮影」と言います。
X線や放射線などを対象物に照射することで臓器の断面画像を撮影する方法なので、立体的(3D)に表示することや、造影剤を利用してより詳しく調べることも可能です。
| 項目 | 長所 | 短所 |
|---|---|---|
| 利便性 | 頸部から骨盤まで25秒ほどで検査が終了 (広い範囲の検査に適している) | 病変と正常組織の濃度の差がMRIより不鮮明 |
| リスク | 放射線被ばくリスク | |
| 診断範囲 | 主に肺や腎臓、頭部の検査に有用 (MRIでは骨や肺の描出が難しい) |
【MRI(磁気共鳴画像法)】
MRIは「Magnetic Resonance Imaging」の略で、日本語では「磁気共鳴画像法」と呼ばれる磁石と電磁波を使って臓器や血管などの断層画像を撮影する方法で、4種類の代表的な撮影方法があります。
| 診断方法 | 性質 | 適応 | 高信号域(白) | 低信号域:(黒) |
|---|---|---|---|---|
| T1強調画像 (T1 Weighted Image:T1WI) | X線CTに近似した画像 | 大脳皮質や白質の解剖学的な構造をとらえる上で有用 | 脂肪 出血部位(亜急性期) 骨髄 筋肉 脳白質 脳灰白質 変性 浮腫 | 水(脳脊髄液や尿など) |
| T2強調画像 (T2 Weighted Image: T2WI) | 多くの病変(出血・亜急性期脳梗塞など)を高信号で描出 | 脳梗塞や病変の抽出に有効 | 水(脳脊髄液や尿) 脂肪(皮下組織や骨髄) 脳灰白質 変性 浮腫 脳白質 | 筋肉 |
| 水分抑制画像 (Fluid Attenuated Inversion Recovery FLAIR ) | T2WIの水(脳髄液)からの信号を抑制した画像で脳脊髄液が黒く描出される | 脳室に隣接した病変を特定しやすい | 脳脊髄液 | |
| 拡散強調画像 (Diffusion Weighted Image DWI) | 水分子の拡散運動を画像化 拡散運動が低下した部位が高信号で描写する | 超急性期(発症直後)の脳虚血性病変診断に有効 | 超急性期および急性期の脳梗塞 |
【MRI(磁気共鳴画像法)】では、詳細な画像診断ができますが、閉鎖空間で操作音があったり、時間がかかることなどから撮影が困難なケースが多いことがデメリットです。
| 項目 | 長所 | 短所 |
|---|---|---|
| 利便性 | 病変部と正常組織のコントラストが良好 横断像だけでなく、冠状断像や縦断像も描写可 造影剤を使わなくても血管や胆管などが映し出せる | 検査の範囲が狭い 撮影に時間がかかる(30分~1時間) 閉鎖空間で行う |
| リスク | X線被爆の心配がない | |
| 診断範囲 | 「脊髄」「内臓」「血管」まであらゆる部位 | 骨の変化がわかりにくい |