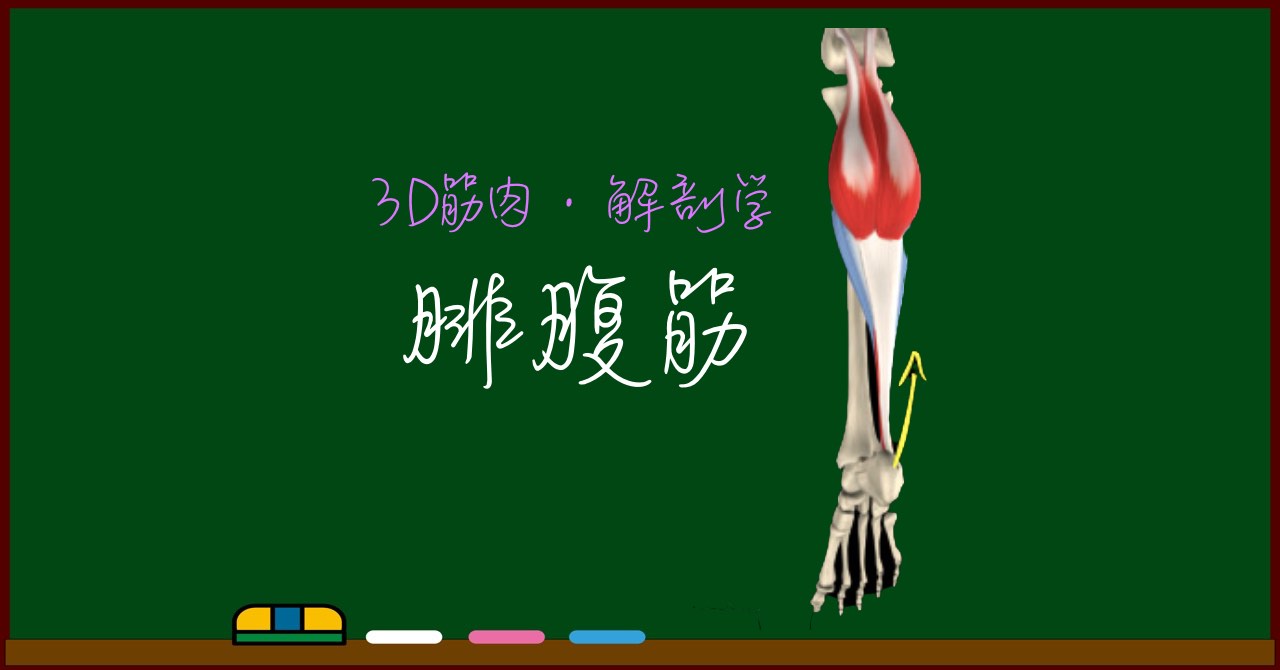第二の心臓と呼ばれる「ふくらはぎ」の筋肉【下腿三頭筋(「腓腹筋」+「ヒラメ筋」)】解剖学構造(起始停止、作用、神経支配)についてイラスト図解でわかりやすく説明しています。
【下腿三頭筋(腓腹筋とヒラメ筋)】とは?どこにあるどんな筋肉?
【下腿三頭筋】は下腿後面表層の筋肉群に分類される筋肉群のうち、「腓腹筋」と「ヒラメ筋」の総称で、いわゆる「ふくらはぎの筋肉」のことです。
「腓腹筋」が2頭のため、筋肉は2つですが3頭筋と呼びます。
| 筋肉名 | 筋肉名(ふりがな) | 英語 |
|---|---|---|
| 腓腹筋 | ひふくきん | Gastrocnemius |
| ヒラメ筋 | ひらめきん | Soleus |
ふくらはぎ部分を構成する力強い筋肉である【下腿三頭筋】は、直立歩行を獲得した人間のために発達した筋肉群で、立位保持、歩行、ジャンプ、血液循環促進など二歩足歩行の人間の活動に欠かせない重要な役割を担っています。
【腓腹筋】と【ヒラメ筋】の力強い筋腹はアキレス腱となり踵に停止していますが、人差し指くらいの太さのアキレス腱が支えることができる重量は1トンほどと言われています。
また、二本足歩行をする動物である私たち人間の生活では、重力の影響で下半身に血液の70%が集まってしまうため、心臓のポンプ機能を補う(血液を心臓に戻す働き)必要があります。
そこで、【下腿三頭筋】を「第二の心臓」と呼ばれるくらい、四本足動物よりも高度に発達させ、下に滞りがちな血液を心臓に戻しています。
脚のむくみや疲れやすさ、冷えなどが気になる場合は、第二の心臓と呼ばれる【下腿三頭筋】を正しい解剖学知識を持って鍛えて全身の循環を改善することで、きゅっと引きしまったふくらはぎや足首のある美脚はもちろん、ダイエット・美肌・冷え性や肩こりの改善など様々な健康効果が期待できます。
【腓腹筋】とは?どこにあるどんな筋肉?
【腓腹筋】は、大腿骨から膝関節を経由して起始し、ふくらはぎ(下腿後面)最表層部分で大きな筋腹を作る力強い筋肉です。
ギリシャ語でお腹(胃)を意味する「γαστήρ (gaster) 」脚を意味する「κνήμη (kneme)」から名前がつけられた【腓腹筋(Gastrocnemius)】は、まさに「足のお腹」のような形状と重要な機能を持っています。
【ヒラメ筋】とは?どこにあるどんな筋肉?
【ヒラメ筋】は広い平な筋肉で、膝下から【腓腹筋】直下を走行しています。
「膝関節」の角度に影響される二関節筋の【腓腹筋】とは異なり、【ヒラメ筋】は純粋な「足関節底屈筋」として強い力を発揮して「腓腹筋」の作用をサポートし、抗重力筋として立位保持を維持するために常に収縮しています。
【下腿三頭筋(腓腹筋とヒラメ筋)】起始停止
【下腿三頭筋】は、【腓腹筋】は大腿骨から2頭、【ヒラメ筋】は下腿骨(脛骨・腓骨)から1頭の合計3頭で起始します。
【腓腹筋】は膝窩下縁でひとつの筋腹になり、その下を併走するうように走行する【腓腹筋】と共に下腿中央あたりまで筋腹を広げたあと、徐々に筋腹を狭めて共にアキレス腱となり合して「踵骨」に停止します。
| 起始 | |
|---|---|
| 腓腹筋 外側頭 | 大腿骨外側上顆後外側面 外側顆上線 |
| 腓腹筋 内側頭 | 大腿骨内側上顆後面 大腿骨骨幹部軸膝窩面 |
| ヒラメ筋 | ヒラメ筋線 腓骨内側縁 腓骨頭 腓骨後縁 |
【腓腹筋】解剖学構造
【腓腹筋】外側頭は「大腿二頭筋」腱と一部重なり、【腓腹筋】内側頭は「半膜様筋」に覆われていて、いずれも「膝関節包」にも含まれます。
【腓腹筋】外側頭と内側頭は、膝窩下縁で合してひとつの筋腹になり、いわゆる「ふくらはぎ」部分となります。
【腓腹筋】表層は筋膜で覆われ、小さい伏在静脈や腓骨の連絡神経や腓腹神経と隔離されていて、【腓腹筋】深層は、膝窩筋靭帯、膝窩筋、【ヒラメ筋】、「足底筋、膝窩動脈および静脈、脛骨神経と接しています。
【ヒラメ筋】解剖学構造
【ヒラメ筋】深層は、筋間中隔によって隔てられ、「長趾屈筋」「長母趾屈筋」「後脛骨筋」「後脛骨動脈と静脈」および「脛骨神経」があります。
【下腿三頭筋(腓腹筋とヒラメ筋)】作用
【下腿三頭筋(腓腹筋とヒラメ筋)】は足関節底屈の主動作筋で、歩行やジャンプなどの際に重力に抗して踵を持ち上げる時などに強く作用します。
| 関節 | 作用 | |
|---|---|---|
| 腓腹筋 | 膝関節 | 屈曲 |
| 腓腹筋 | 足関節 (距腿関節) | 底屈(踵挙上) |
| ヒラメ筋 | 足関節(距腿関節) | 底屈(踵挙上) |
【腓腹筋】と【ヒラメ筋】は【下腿三頭筋】として協力しあって共に作用しますが、得意分野が違いますので、それぞれの作用の違いも整理しておきましょう。
【腓腹筋】作用
【腓腹筋】は膝関節屈曲にも関与する二関節筋で、瞬間的に力強い底屈運動を起こす筋肉なので、ジャンプや歩行時の蹴り出しなど運動を起こす時に強く働きます。
【ヒラメ筋】作用
【腓腹筋】深層にある【ヒラメ筋】は純粋は足関節底屈筋ですが、「脊柱起立筋群」「大臀筋」「ハムストリング」などと共に立位を保持するための抗重力筋(姿勢保持筋)として重力に対して常に収縮しています。
【ヒラメ筋】は歩いたり立っている時に常に収縮しているので、【ヒラメ筋】は遅筋(疲労しにくい繊維)が多く含まれています。
【腓腹筋】と【ヒラメ筋】のチームワーク作用
【下腿三頭筋】は、【腓腹筋】と【ヒラメ筋】の絶妙なチームワークで機能するユニットのようなものです。
人間の身体の重心は足首前面を通る垂直線で動くため身体はもともと前傾しやすくなっていますが、【ヒラメ筋】が常に収縮して後ろに引くことで立位の安定性が保たれますし、【ヒラメ筋】による安定した土台があってこそ、【腓腹筋】による歩行、ダッシュ、ジャンプなどの力強い運動が可能となります。
また、【腓腹筋】は膝関節にも作用する二関節筋なので、膝関節の角度により【腓腹筋】足関節底屈力が制限されてしまいますが、【ヒラメ筋】は膝関節屈曲角度に関わらず一定の張力を発揮できます。
【下腿三頭筋(腓腹筋とヒラメ筋)】神経支配
【下腿三頭筋(腓腹筋とヒラメ筋)】は、「脛骨神経(S1、S2)」支配です。
【下腿三頭筋(腓腹筋とヒラメ筋)】触診
【腓腹筋】は、ふくらはぎの盛り上がりを作っている筋肉なので簡単に触診できます。
【ヒラメ筋】の収縮は膝関節の屈曲角度に変化をつけることで、【腓腹筋】と区別しやすくなります。
【下腿三頭筋(腓腹筋とヒラメ筋)】ストレッチと筋トレ
ふくらはぎの筋肉である【下腿三頭筋(腓腹筋とヒラメ筋)】を鍛えることは、脚(下半身)の安定性を高める効果や心臓の負担を軽減して全身の血流や循環を改善する効果も期待できるため、高血圧や心臓血管系の症状の予防・改善、美肌・ダイエット・冷え性・むくみ・血栓症改善など多様な健康効果、上半身をリラックスさせて肩こり・首こりなどの根本解消につながるケースも多くあります。
キュッと引き締まったふくらはぎのラインは、美しい脚のラインに欠かせない要素でもありますので、解剖学構造を理解して効果的に美脚作り・ボディメイクをしましょう。
【下腿三頭筋(腓腹筋とヒラメ筋)】ストレッチやマッサージをする時は、循環を促すために、足首周りのストレッチや背面全体の筋膜の繋がりも意識して行いましょう。
【下腿三頭筋(腓腹筋とヒラメ筋)】トレーニングの際は、膝関節の角度や負荷のかけ方で【ヒラメ筋】と【腓腹筋】を区別することでより効果的なボディメイクやパフォーマンス向上が期待できます。