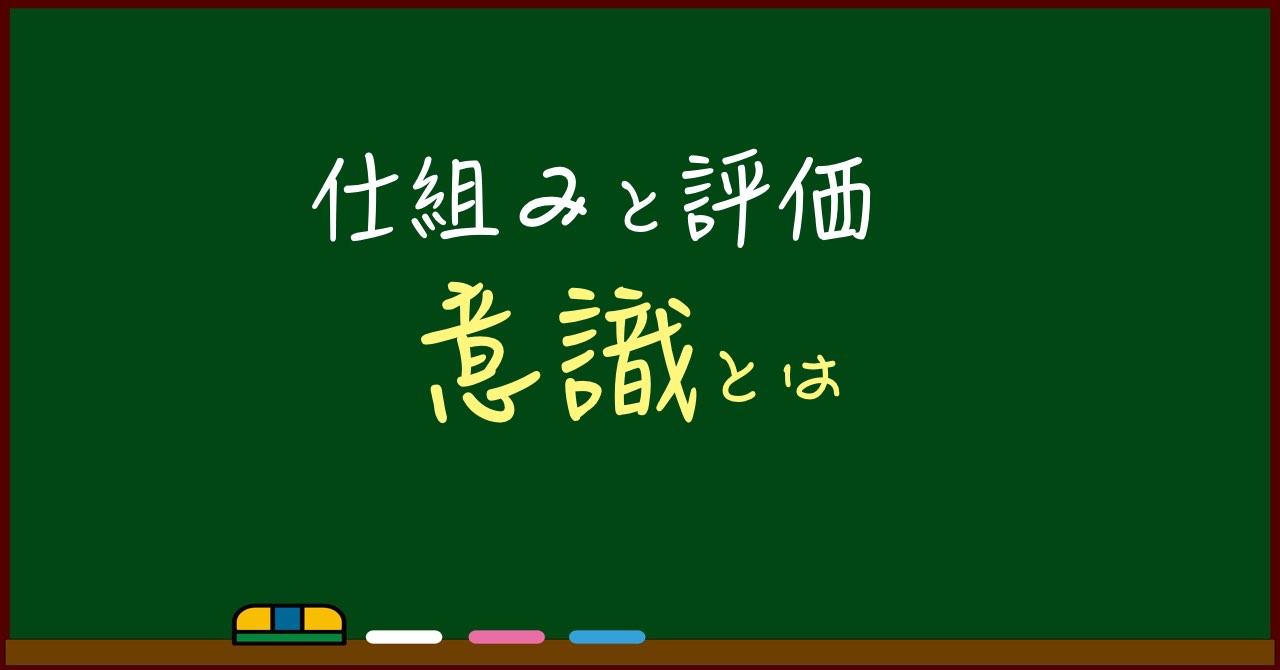「意識」は私たちの意図的な活動の前提となる脳機能です。
意識が正常な状態と意識障害の判別、意識の程度を客観的に状態を把握できる評価(指標)について整理してまとめました。
「意識」とは?
「意識」とは、私たちの意図的な活動の前提となる脳機能で、「意識がある状態」では外部の情報を認識して適切な反応ができます。
- 目を覚ましていて
- 外からの刺激に何らかの反応を示し
- その刺激を正しく認識して
- 適切に対応することができ
- その時の行動を覚えている
「意識」中枢と仕組み
意識の中枢は、「大脳皮質」と「上行性網様体(橋上部~中脳にかけての脳幹網様体)」です。
「末梢器官」で受け取った感覚刺激は、神経線維を通じて「脳幹」に情報が伝達され、「視床網様体賦活系」が働くことで感覚情報の統合と整理が行われます。
統合された情報は「視床」を経由して、大脳の「知覚領域」「視床下部」「大脳辺縁系」に達し、認知した感覚刺激に対する適切な反応を末梢に起こさせる指令を出します。
刺激に対して起こした反応もまた同じ経路でフィードバックされて脳に記憶されます。
「意識」評価指標
「意識」評価は原則「量」で行いますが、軽度の意識障害の場合は反応のスピードや反応の内容など「質」でも評価する必要があります。
意識障害の程度を客観的かつ経時的に評価できるスケールを2つ紹介します。
GCS(グラスゴー・コーマ・スケール:Glasgow Coma Scale)
GCS(グラスゴー・コーマ・スケール)は、外傷性脳障害による意識障害を評価することを目的に作成された指標で、「外傷性脳障害」「クモ膜下出血」「細菌性髄膜炎」「蘇生後脳症」などの疾患症例の予後推定に有用とされています。
E 開眼(eye opening) E4 自発的に開眼 E3 呼びかけにより開眼 E2 痛み刺激により開眼 E1 痛み刺激により開眼なし V 最良言語反応(best verbal response) V5 見当識あり V4 混乱した会話(見当識障害あり) V3 不適当な発語(単語) V2 理解不明の音声(アーアーなど) V1 発語みられず T 気管切開(Tracheotomy) A 失語症(Aphasia) M 最良運動反応(best motor response) M6 命令に応じて四肢を動かす M5 痛み刺激に対して手で払いのける M4 痛み刺激に対し四肢を引っ込める(逃避) M3 痛み刺激に対して異常な屈曲運動(除皮質硬直) M2 痛み刺激に対して異常な伸展運動(除脳硬直) M1 運動みられず JCS(ジャパン・コーマ・スケール:Japan Coma Scale)
JCS(ジャパン・コーマ・スケール)は「頭部外傷」や「脳血管障害(クモ膜下出血)」の急性期の脳ヘルニアの進行を評価することを目的に作成された指標です。
Ⅰ 刺激しないでも覚醒している状態 0 意識清明 1 見当識は保たれているが意識清明ではない 2 見当識障害がある 3 自分の名前・生年月日が言えない Ⅱ 刺激すると覚醒する状態 10 普通の呼びかけで容易に開眼する 20 大きな声または身体を揺さぶることにより開眼する 30 痛み刺激を加えつつ呼びかけを続けると辛うじて開眼する Ⅲ 刺激をしても覚醒しない状態 100 痛み刺激に対し払いのけるような動作をする 200 痛み刺激で少し手足を動かしたり顔をしかめる 300 痛み刺激に全く反応しない いずれもその意識レベルの相当する最強の刺激から得られる反応の中で、最も良い反応で評価します。
また、必要に応じて以下を追記します。
- R:Restlessness(不隠)
- I:Incontinence(失禁)
- A:Apallic state(失外套症候群)またはAkinetic mutism(無言無動)
「熟睡」と「意識障害」違いを判別
「死んだように眠る」という表現がありますが、私たちは熟睡しているときはちょっとやそっとの刺激では反応しないし、起きない場合もあります。
「熟睡している意識清明」と「意識障害の鑑別」は、上記で紹介したスケールでは、刺激で覚醒した後15秒観察して15秒以内に閉眼(意識レベルが下がる)なら「意識障害」と評価しています。
意識障害は、徐々に進行する場合もあれば急速に悪化する場合もあるため、血圧、呼吸障害などのバイタルサインとともに経時的に観察する必要があります。
「空腹」「睡眠不足」「疲労」などでも意識レベルが低下することはあり得ますので、意識の低下や消失の背景に何があるのか、他にはどんな症状が出ているのか、継時的な変化はどうか、など様々な角度から情報を取り、統合させていくことで正しい判断ができます。
「意識障害」原因
「意識障害」には様々な原因があります。
一次性中枢性神経系意識障害(脳に原因がある場合)
意識の中枢である脳に障害がある場合は、意識障害が生じます。
- 脳血管障害
- 頭部外傷
- 脳腫瘍
- 中枢神経系感染症
- 痙攣発作(てんかん)
二次性中枢性神経系意識障害(脳以外に直接的な原因がある場合)
脳以外の臓器に機能障害があり、二次的に脳全体が障害される場合も意識障害が起こり得ます。
- 肝性昏睡
- 尿毒症
- 糖尿病性昏睡
- 循環不全
- 呼吸不全
- 水・電解質異常
- 中毒
- 酸素欠乏症
- ヒステリー
一時的な体調不良
「空腹」「睡眠不足」「疲労」などでも意識レベルが低下することはあり得ます。