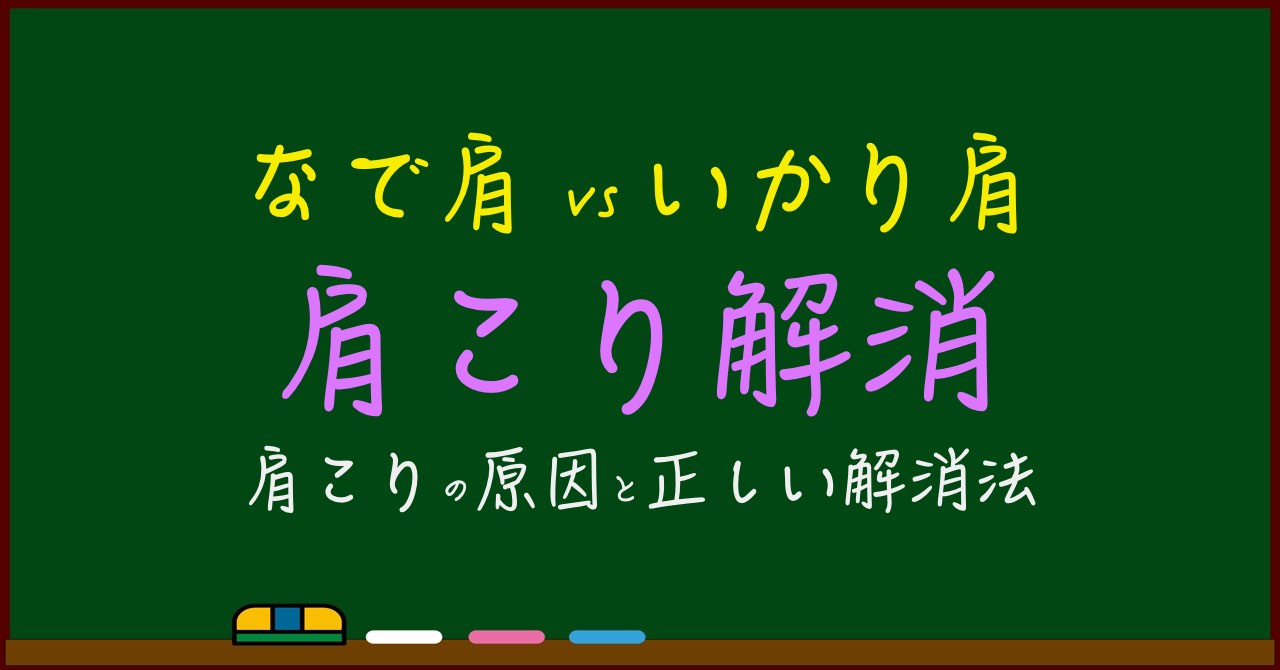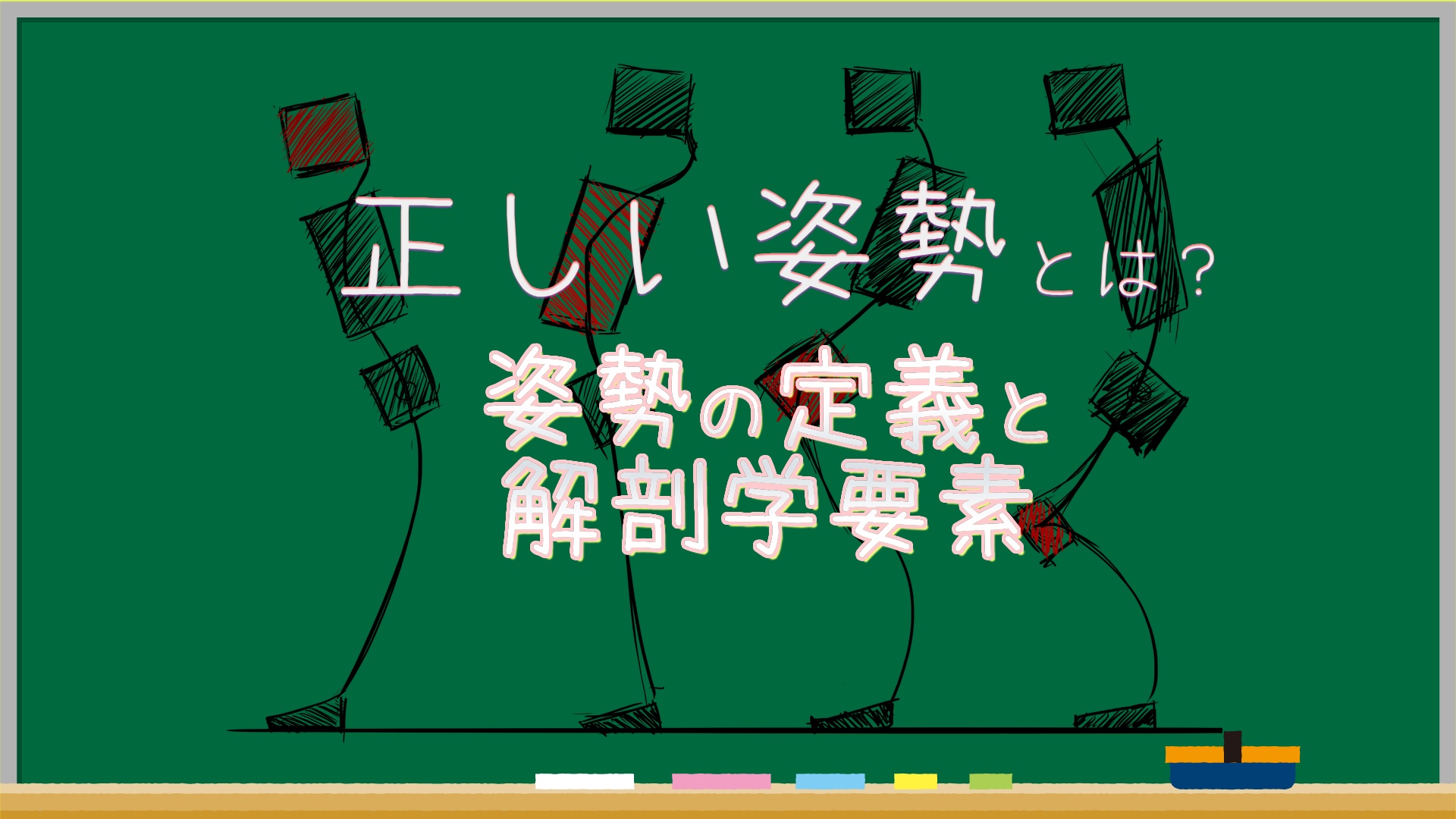「なで肩」「いかり肩」「巻き肩」など、肩周りの印象は、姿勢や見た目全体に大きく影響しますし、肩周りの変化を放置すると、カチカチ肩こり、上半身のだる重さ、腕が上がりにくだけでなくジンジンと腕や手の痺れも感じる五十肩(四十肩)などの原因になることもあります。
肩の状態別に、正しく肩こりや五十肩(四十肩)の予防改善する方法や理想のスタイルに近づくためのボディメイクトレーニングについてまとめました。
肩周りは姿勢の顔!
「なで肩」「いかり肩」「巻き肩」など、肩のアライメント(骨格)の特徴を示す呼び方がいくつかありますが、顔の下かつ上半身の一番上にある肩周りは、立っていても座っていても姿勢を特徴つける主要要素であり、相対的に顔の大きさや首の長さ(の印象)、ボディ全体の印象にも影響します。
姿勢の特徴でよく使われる「なで肩」や「いかり肩」、不良姿勢の代表格と「巻き肩(猫背)」、逆三角形ボディを作る時に三角筋、僧帽筋、上腕三頭筋など肩周りの筋肉肥大を目指すこと、などがわかりやすい例だと思います。
肩周りの特徴は自分でデザインできる?
「なで肩」「いかり肩」など肩周りの印象は生まれつきだと思っている人も多いかもしれません。
もちろん、肩の骨格自体は生まれつきの要素も大きいですが、「なで肩」「いかり肩」「巻き肩(猫背)」は、ほとんどのケースで筋肉の鍛え方や姿勢への意識の仕方で、綺麗な肩のライン(総合的に理想のボディライン)に変えられます。
例えば、逆三角形ボディを目指すボディメイクでは、三角筋、僧帽筋、上腕三頭筋など肩周りのラインに変化をつけるような筋肥大トレーニングをよく行いますが、これは肩周りの印象を大きく変えることでボディライン全体の印象を効果的に変えることができるためです。
また、「なで肩」「いかり肩」「巻き肩(猫背)」などの姿勢変化で表現される肩のアライメント(骨格)は、普段の生活姿勢の問題や肩周辺の筋肉のアンバランスにより生じているので、単純に見た目の問題だけでなく「肩こり」や「五十肩(四十肩)」など肩の運動制限、肩こり、首や腕の痛みなどの問題と直接的に関連しています。
つまり、肩周りの筋肉を正しく鍛えて姿勢を整えれば、理想のボディラインを作ると同時に「肩こり」や「五十肩(四十肩)」など肩の運動制限や痛みなどの問題も予防解消できます。
肩周りの印象を決める筋肉群の解剖学(特徴と作用)
肩甲骨の動きを含む肩関節(肩甲帯)には、様々な作用を持つ筋肉が付着していますが、それらの筋肉の緊張や筋力のアンバランスが生じると、「なで肩」「いかり肩」「巻き肩(猫背)」の原因になり、それらを放置することで、腕や首のしびれや痛み、腕の上がりにくさなどにつながります。
肩のラインを含む姿勢に大きく影響する筋肉は主に以下の筋肉群です。
| 筋肉名 | 解剖学特徴 | 姿勢への影響(主な作用) |
|---|---|---|
| 僧帽筋 | 首・肩・背中上部を広範囲に覆う大きな最表層筋肉で、上部・中部・下部で作用が異なる | 上部は肩甲骨挙上、中部はリトラクション、下部は下制に作用。 |
| 肩甲挙筋 | 僧帽筋下部で上部頸椎から肩甲骨の内側縁上部に向かって走行 | 名前の通り肩甲骨を上(頸椎の方向)に引く作用が強力。 |
| 菱形筋 | 左右の肩甲骨内側縁と背骨をつなぐように走行して肩甲骨を安定させている | プロトラクションの抑制に作用。上部繊維は僧帽筋や肩甲挙筋の作用を補助。 |
| 前鋸筋 | 肋骨から肩甲骨前面に向かって走行して肩甲骨を胸郭に安定させている筋肉 | 肩甲骨を前外側引く作用の他、下部繊維は肩甲骨引き下げにも作用。 |
| 小胸筋 | 肋骨前面から肩甲骨内側縁と烏口突起に向かって走行し、肩甲骨を胸郭に安定させている筋肉 | 肩甲骨を前下方へ引く作用があり、「前鋸筋」が一緒に「肩甲骨プロトラクション」に作用。 |
肩と姿勢の解剖学〜「なで肩」「いかり肩」「巻き肩(猫背)」定義と違い
「なで肩」「いかり肩」「巻き肩(猫背)」は生まれつきの姿勢の特徴というよりも、不良姿勢や筋肉のアンバランスが慢性化した結果であることが多いのですが、それらの特徴を解剖学で生理しています。
まず、「なで肩」と「いかり肩」は前額面における肩のラインの差で、鎖骨の胸骨側(内側)に対して肩甲骨側(外側)がどの程度上がっているかがひとつの目安となります。
「巻き肩(猫背)」は矢上面での変化で、「なで肩」でも「いかり肩」でも、そのどちらでもなくても生じます。
| 見た目の特徴 | 解剖学的特徴 | |
|---|---|---|
| 良い姿勢の肩 | 解剖学上ニュートラル | 鎖骨角度5°以上10°未満 |
| なで肩 | 肩先が下がっている | 鎖骨角度5°未満 |
| いかり肩 | 肩先が上がっている | 鎖骨角度10°以上 |
| 巻き肩 | 肩が前内側に巻き込まれている | 肩甲骨プロトラクション |
肩のラインは左右差も大きくでやすい身体部位なので、左右差に注目することも重要です。
【いかり肩】解剖学
【いかり肩】の特徴は肩先(鎖骨の外側)が上がっていることで、典型的な肩こり姿勢とも言われます。
【いかり肩】を作る主原因筋は、肩甲骨を挙上する強い作用がある「僧帽筋」と「肩甲挙筋」で、これらの筋肉群が凝り固まることで、肩甲骨が挙上したまま固定され、いわゆる肩がすくんだ姿勢になり、【いかり肩】と呼ばれます。
| 筋肉名 | 主な問題点 |
|---|---|
| 僧帽筋 | 上部繊維が短縮して硬くなり、下部繊維が働きにくい(筋力低下) |
| 肩甲挙筋 | 短縮して硬くなっている |
| 小菱形筋 | 短縮して硬くなっている |
特に「僧帽筋」は面積も大きく表層で触診もしやすい筋肉なので、マッサージされるとすぐに気持ちよくほぐれていく感覚からも「肩こり」と自覚しやすい特徴があります。
「肩甲挙筋」は、肩が下がらないように肩甲骨を胸郭に安定させる重要な作用を持っていますが、肩甲骨挙上作用のある筋肉が短縮して硬くなったり、拮抗してバランスをとる肩甲骨を引き下げる作用が低下したりしていると【いかり肩】が定着しやすくなります。
緊張したり、パソコンを使用する時など猫背姿勢で頭が前に出ている時も【いかり肩】になりがちなので、肩こりに悩む人の多くが【いかり肩】と巻き肩(猫背)のセットです。
【なで肩】解剖学
【なで肩】は肩先(鎖骨の外側)が下がっていることが特徴です。
つまり、筋肉解剖学の観点で見ると、自分の腕の重みにすら耐えられないくらい肩甲骨挙上作用のある筋肉(僧帽筋上部繊維)の筋力が低下している状態です。
| 筋肉名 | 主な問題点 |
|---|---|
| 僧帽筋(上部) | 筋力低下(緊張がゆるんでいる) |
| 肩甲挙筋 | 引き延ばされて硬くなる |
| 小菱形筋 | 引き延ばされて硬くなる |
筋力が低下している(収縮力が弱い)状態でも、重力に対して腕を空間に保つために頑張らないといけないので、肩甲骨居城作用のある筋肉群が引き伸ばされた状態で固く凝り固まってしまいます。
【なで肩】の方が、「いかり肩」よりも深層にある筋肉の負担が大きくなっているのですが、一番表層の「僧帽筋」が緩んでいるので「肩こり」を自覚しにくいという特徴があります。
【巻き肩】解剖学
【巻き肩】は姿勢のフォーカスを背骨に移せば「猫背」のことで、「いかり肩」でも「なで肩」でも起こる矢状面での肩周りの変化(肩甲骨が胸郭に沿って前外側に動く)です。
| 筋肉名 | 特徴 |
|---|---|
| 菱形筋 | 引き延ばされて筋力低下(プロトラクション抑制作用低下) |
| 前鋸筋 | 短縮して硬化(肩甲骨プロトラクションに作用) |
| 小胸筋 | 短縮して硬化(肩甲骨プロトラクションに作用) |
「小胸筋」と「前鋸筋」が一緒に作用すると生じる動きである「肩甲骨プロトラクション(肩甲骨が胸郭に沿って前外側に動く)」は、腕を前方に伸ばす時にとても重要な働き(作用)です。
ただ、パソコンを使った机上作業の時間が長い現代人は、どうしても肩甲骨プロトラクションの状態で固定されがちで、これを放置すると様々な健康上の問題が生じてしまいます。
例えば、【巻き肩】(猫背)になると、前に出た頭を引くために「僧帽筋」や「肩甲挙筋」を含む首・肩後面の筋肉が引き延ばされて緊張しづけることで硬くなり、もれなく「肩こり」がセットにもなります。
肩タイプ別!肩こり解消トレーニングの基本的な考え方
特定の不良姿勢が長く続くと、一部の筋肉だけが強く収縮し続けて硬くなるので、硬直した筋肉のそばを走っている血管や神経が圧迫されることで、コリ感、痛み、しびれという症状が出てきます。
その一方で、硬くなった筋肉と反対の作用をする筋肉はゆるんだまま筋力が低下してしまうので、正しいバランスの取れた姿勢に戻しにくくなってどんどん症状が悪化します。
そのため、肩こりを根本的に解消するには、以下の2つのアプローチを同時に行う必要があります。
- 硬くなっている筋肉をほぐして筋肉の弾性を取り戻す(ストレッチや筋膜リリースなど)
- 筋力低下している筋肉を鍛える(筋トレ)
これまで説明してきた通り、「なで肩」「いかり肩」「巻き肩(猫背)」では、短縮している筋肉や緩んでいる筋肉など原因が異なるため、それぞれの肩型や姿勢に適した筋肉へ適切なアプローチをして正常のアライメントに近づけることが目標になります。
| 肩タイプ | キーアプローチ |
|---|---|
| 共通① | 体幹筋肉(コア)を鍛えて背骨から姿勢を整える |
| 共通① | ローテーターカフなど肩周りのインナーマッスルをケアする |
| 【なで肩】 | 腕の重さを支えられるように僧帽筋や三角筋などの筋力を鍛える |
| 【いかり肩】 | 凝り固まった筋肉をほぐして柔軟性を取り戻す→弱化している筋肉を鍛える |
| 【巻き肩】 | 肩甲骨周りの柔軟性を高めるストレッチ + 菱形筋強化 |
「なで肩」「いかり肩」「巻き肩(猫背)」など肩の形状の変化に影響する肩甲骨は、胸郭上を移動し、胸郭は胸椎(背骨)を含む上半身上部の構造なので、背骨のアライメントも正常に保つことも同時に必要になります。
肩こりがある人は腰痛もあることが多いですが、それは肩の状態が背骨に影響する(逆もしかり)からです。