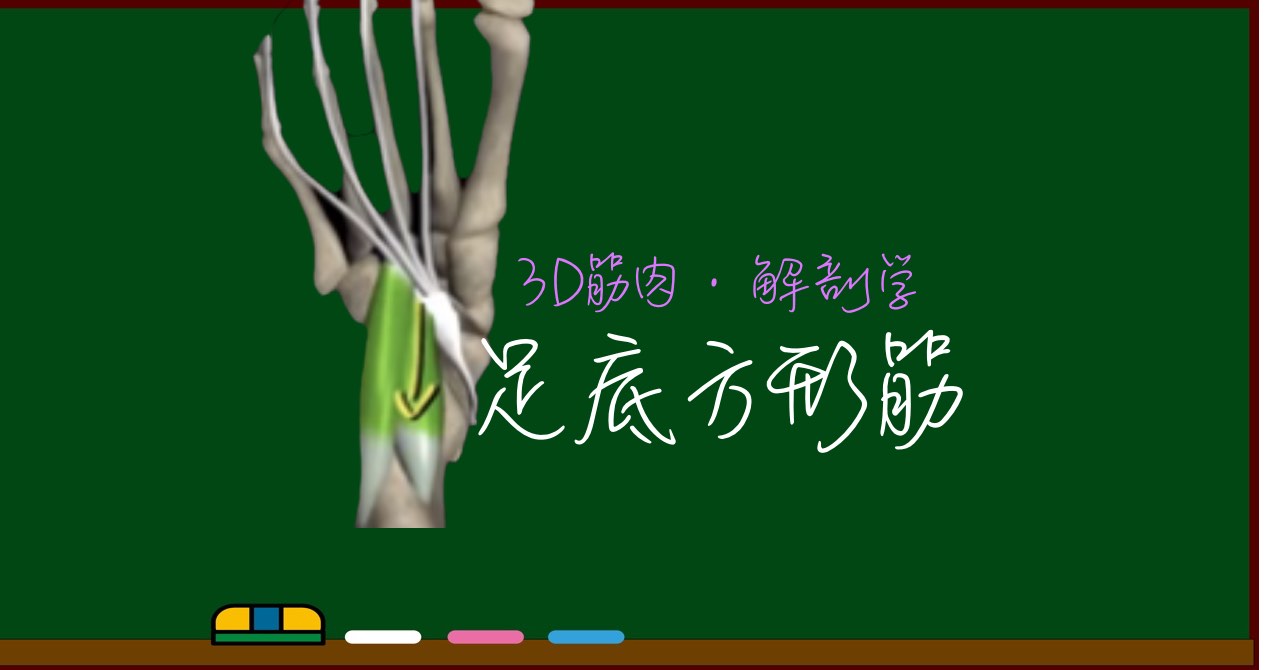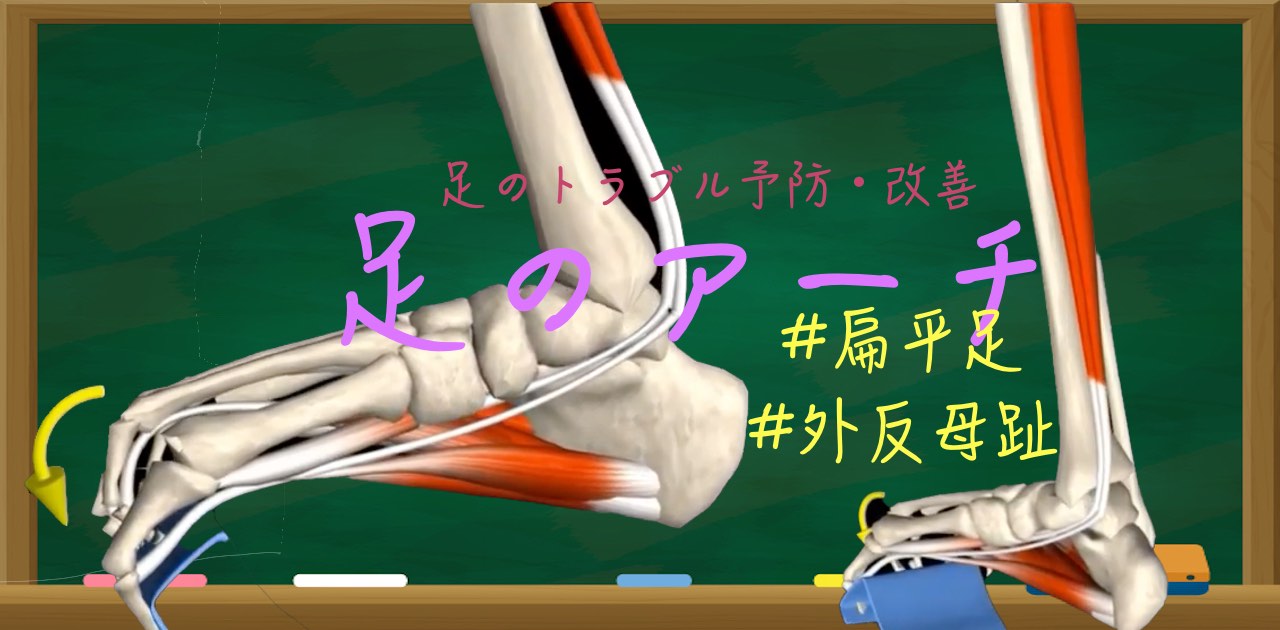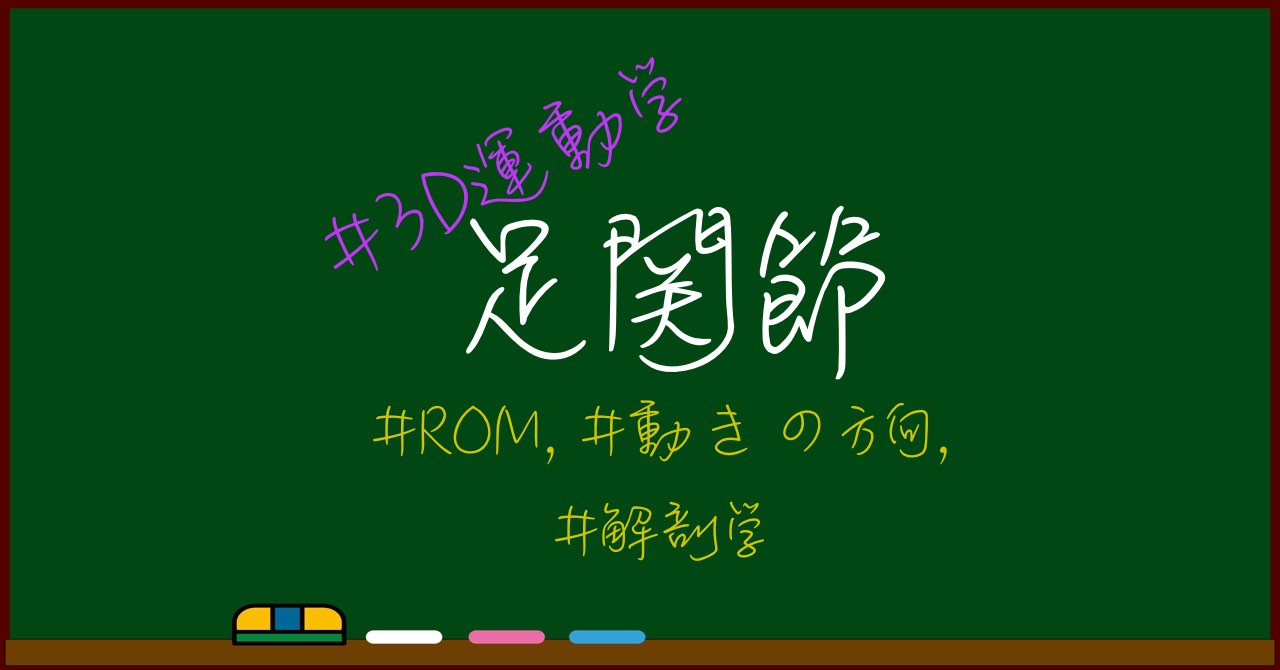【足底方形筋】解剖学構造構造(起始停止、作用、神経支配)についてイラスト図解を使ってわかりやすく説明しています。
【足底方形筋】とは?どこにあるどんな筋肉?
【足底方形筋】は、足底中央部にある筋肉で方形の筋肉で、「足の虫様筋」と共に足底筋第二層に分類されます。
- 名称:足底方形筋
- ふりがな:そくていほうけいきん
- 英語名:Quadratus Plantae
【足底方形筋】は、足の底屈時に「長趾屈筋」を踵へまっすぐ向かう方向へひっぱる(短縮させる)ことで歩行時における「足趾を屈曲する」動作を補強してスムース足趾屈曲を促す作用があるため、「趾屈補助筋」とも呼ばれます。
【足底方形筋】起始停止
【足底方形筋】は、「踵骨」から二頭で起始した筋腹は足底を足先に向かって走行し、4つの腱に別れて「長趾屈筋腱」に停止します。
| 起始 | 停止 |
|---|---|
| 踵骨内側面 踵骨隆起外側突起 | 長趾屈筋腱 |
【足底方形筋】内側頭は「踵骨内側面(長母趾屈筋が付着する踵骨溝のすぐ下)」から、【足底方形筋】外側頭は「踵骨隆起外側突起」から起始しますが、長い足底靭帯で区切られていて、外側頭の方がより小さく腱状です。
稀に外側2つの「長趾屈筋」腱には停止しない場合もあります。
【足底方形筋】作用
【足底方形筋】が収縮すると「長趾屈筋」腱を踵骨に向かって引く作用が生じます。
これは歩行時に足の底屈時(スタンス→スイング)に重要な動きで、足関節底屈ですでに収縮している「長趾屈筋」を短くすることでつま先を曲げる作用を起こせるようにし、結果「長趾屈筋」によるつま先で地面を捉えて足を離す動作ができるようになります。
| 関節 | 作用 |
|---|---|
| 第2~5中足趾節関節 | 屈曲 *「長趾屈筋」作用を強化 |
また、【足底方形筋】があることで、斜めに走行している「長趾屈筋」の作用を踵へまっすぐ向かう方向へひっぱれるので、「足趾を屈曲する」動作が正常にできるようになります。
【足底方形筋】神経支配
【足底方形筋】は、「脛骨神経」に由来する「外側足底神経(S1-S3)」支配です。
【足底方形筋】触診
【足底方形筋】は、母指内転筋」の表層かつ「短趾屈筋」の深層にあり、足底中央部下方で確認できます。
【足底方形筋】表層は、「外側足底動脈および神経」が通過し、内側を「内側足底動脈と神経」が通過します。
【足底方形筋】鍛える方法
【足底方形筋】にアプローチするときは、まず足首や足裏をマッサージして筋肉の緊張をほぐして柔軟性を高めてからから、タオルギャザーで掴む運動を意識して行います。
足部全体の構造を理解してトレーニングやコンディショニングを実践するとより効果的です。