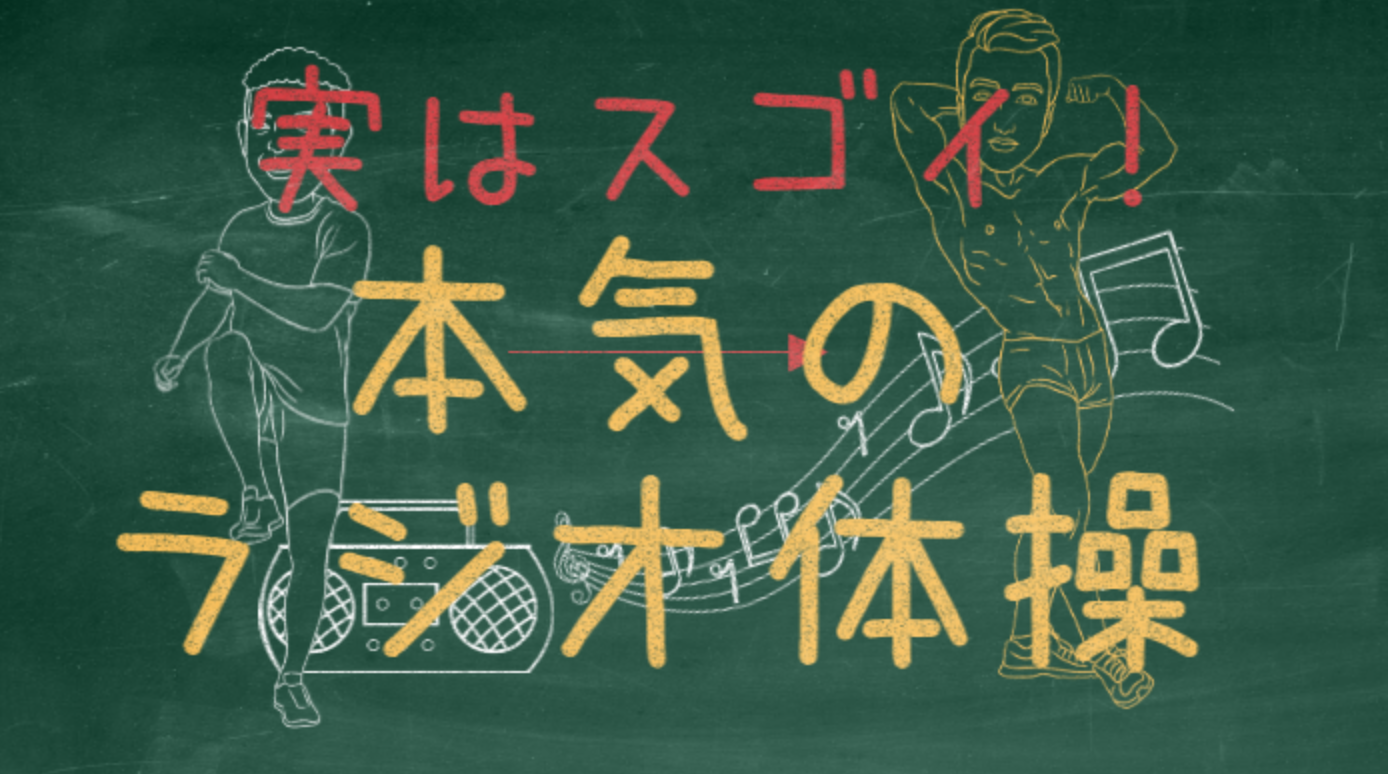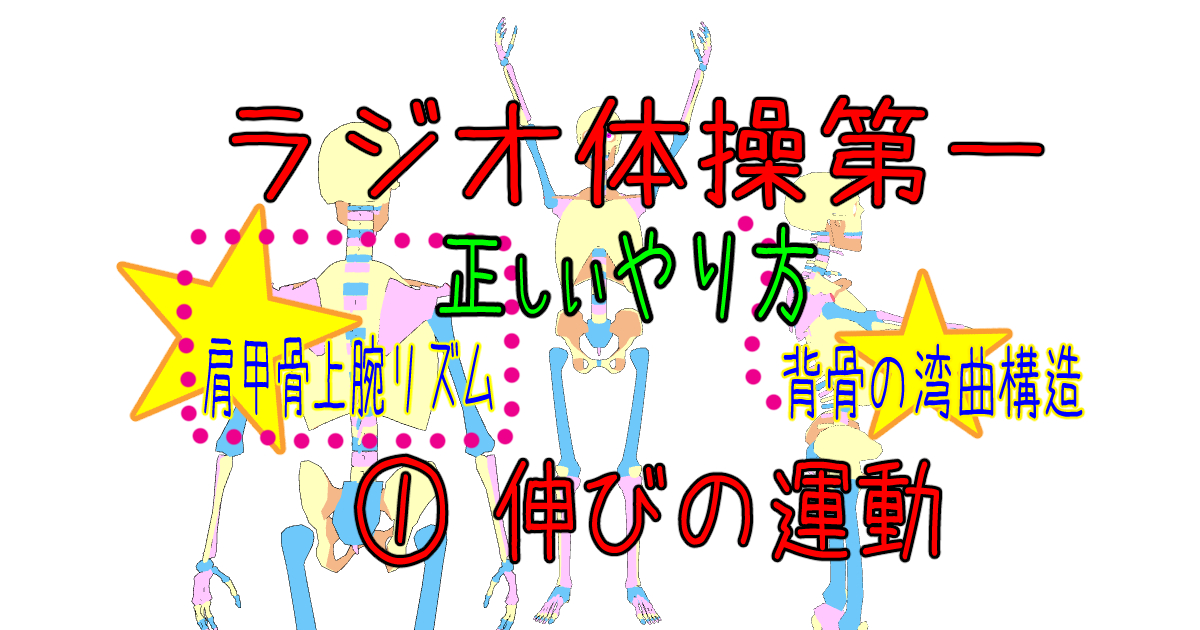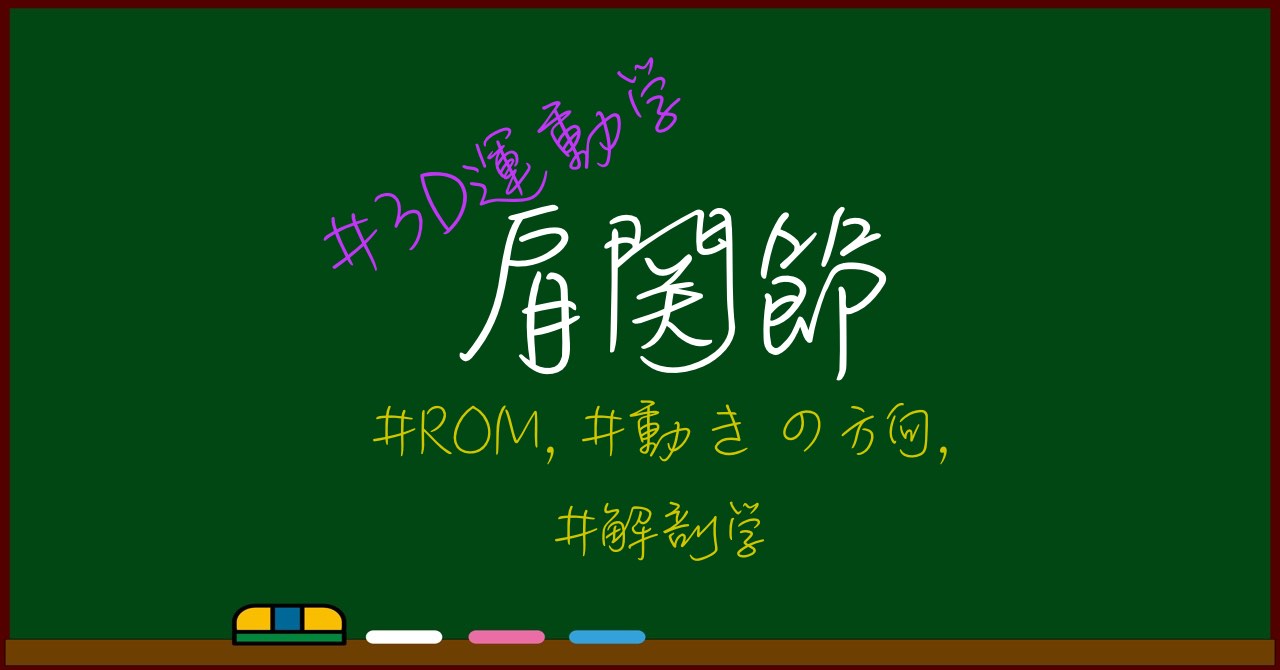たった3分で全身がととのう最強エクササイズ!「【ラジオ体操第二】⑨体をねじり反らせて斜め下に曲げる運動」を解剖学と運動学の視点から分析し、うまくできない時の軽減方法やなりたいスタイルや目的に合わせたアレンジも提案します。
【ラジオ体操】3分で全身筋トレできる最強エクササイズ!
みんなやったことがあるけれど正しくできるいる人が意外に少ない「ラジオ体操」ですが、実はたった3分で全身をバランスよく整える美容健康効果に優れた最強エクササイズです。
【ラジオ体操第二】「老若男女を問わず誰でもできることにポイントを置いたラジオ体操第一」よりも運動負荷が大きく、体を鍛えて筋力を強化することをポイントにおいています。
面白いのが、同じ名前の体操でも【ラジオ体操第一】と【ラジオ体操第二】で動きや注目ポイントが異なるので、第一と第二を組み合わせると、更なる美容健康効果が期待できます。
みんなやったことがあるけれど正しくできるいる人が意外に少ない「ラジオ体操」ですが、実はたった3分で全身をバランスよく整える美容健康効果に優れた最強エクササイズです。
「ダイエットやボディメイクをしたいけれど何から始めたらよいかわからない」「運動を始めたいけど難しいのは続かない」なら、まず「ラジオ体操」を極めてみることをオススメします!
【⑨体をねじり反らせて斜め下に曲げる運動】ラジオ体操の正しいやり方と解剖学
「【ラジオ体操第二】⑨体をねじり反らせて斜め下に曲げる運動」は、「ダイナミックな動きで胴体全体をほぐす」目的のエクササイズで以下の効果が期待できると公式サイトには記載されています。
公式サイトより引用
- 腰痛予防
- 正しい姿勢づくり
- 柔軟性アップ
重要な運動要素
「【ラジオ体操第二】⑨体をねじり反らせて斜め下に曲げる運動」は、「背骨の回旋運動」「胸を開く広げる運動」「股関節の屈伸運動」の組み合わせで、上半身の柔軟性を向上させつつ、姿勢を整えて保持する筋力を鍛える効果に優れています。
| 重要な運動 | 目的 |
|---|---|
| 背骨の回旋運動 | 背骨の機能を高める 上半身の柔軟性を高める 神経機能を整える |
| 胸を開く広げる運動 | 呼吸を深める 背骨周囲の機能や柔軟性を高める |
| 股関節の屈伸運動 | 上半身と下半身をつなぐ腹腔まわりの筋肉を鍛える |
胸を開いて呼吸を深める要素を加えながら行う「背骨の回旋運動」は、内臓マッサージ効果で内臓器官の働きを促進し、お腹周りを囲むコルセットである「腹横筋」「腹斜筋」「腰方形筋」を左右バランスよく鍛えて体幹を強化し、腰痛予防効果も期待できます。
なんとなく腰周りを動かすのではなく、ひとつひとつの運動要素を意識することで柔軟性のある正しい姿勢作りにつながります。
準備姿勢(スタートポジション)
「【ラジオ体操第二】⑨体をねじり反らせて斜め下に曲げる運動」の準備姿勢(スタートポジション)は、「【ラジオ体操第一】①伸びの運動」と同じ背骨と骨盤をニュートラルした良い姿勢を基準に、脚は肩幅よりも広く真横に開き土台を安定させます。
更に、腕は肩の高さに上げて(肩関節を90度)程度屈曲し、腕で誘導しながら背骨を回旋させる準備をします。
運動方向と可動域
「【ラジオ体操第二】⑨体をねじり反らせて斜め下に曲げる運動」のやり方は公式サイトでは以下のように説明されていますが、解剖学でより要素を分解することで、意識するポイントがわかりやすくなります。
公式サイトより引用
- 準備姿勢
- 両腕を斜め上に大きく振り上げ
- 上体をねじり反らせ
- 右下にはずみをつけて2回曲げる
- 上体を起こしながら準備姿勢に(反対側)
解剖学でより細かい運動要素に分けると「股関節の屈伸運動」「背骨の回旋運動」「背骨(主に胸椎)の屈伸運動」の組み合わせに、背骨や股関節の運動方向へ誘導するための肩関節の運動が加わります。
| パーツ | 運動方向 |
|---|---|
| 股関節 | 屈曲⇄伸展 |
| 背骨 | 回旋(腰椎中心) 屈曲⇄伸展(胸椎中心) |
| 肩関節 | 背骨の運動方向を誘導 |
「ラジオ体操効果を高めるコツ」と「よくある間違い(対処法)」
公式サイトではやり方のコツとして以下のように記載されています。
動きを止めず、滑らかに運動しましょう
公式サイトより引用
この体操は、「背骨の回旋運動」「股関節の屈伸運動」「胸椎(胸郭)の伸展」「胸郭の動きに連動した肩関節の運動」と様々な要素が組み合わせてありますので、最初がぎこちなくなってしまうかもしれません。
| 運動要素 | 効果を高めるコツ |
|---|---|
| 股関節運動 | 下半身を安定させる 背骨の軸は維持する |
| 両腕の運動 | 腕と体幹のつながりを意識する 腕の動きで運動方向や負荷を調整する |
背骨の軸は維持したまま、上半身の余計な力を抜いて股関節から上半身を大きくまわすイメージで行いましょう。
背骨の軸を維持したまま股関節運動
下半身は最初の基本姿勢のまましっかり安定させておくことで、安全に股関節運動が行えます。
前屈する時は首や肩の力は完全に抜いて背骨も自然なカーブを保ちますが、上半身を起こす時は腰に負担をかけないように軸をしっかり保ったままお尻や太もも裏の筋肉で行うようにしましょう。
動かす椎骨(背骨の部位)を意識する
斜め方向に股関節前屈する時は、腰椎から背骨全体を回旋させますが、上体反らしの時は背骨を反らすというよりも、胸を開いて呼吸を深めることに集中します。
背骨全体を反ろうとすると、腰や首に負担がかかってしまいますので、胸椎を伸ばして背骨を長くしながら胸を広げるイメージを持つことで、運動効果を高められます。
腕と上半身のつながりを意識する
肩関節(腕)の運動は自重や遠心力でターゲットとなる体幹の動きを出しやすくしたり、適切な負荷を加えるためのものなので、肩や腕の余計な力を抜いて、正しい運動方向へ誘導するように動かしましょう。
また、目線も腕の方向に合わせることで、筋膜のつながりにそった滑らかな動きになります。