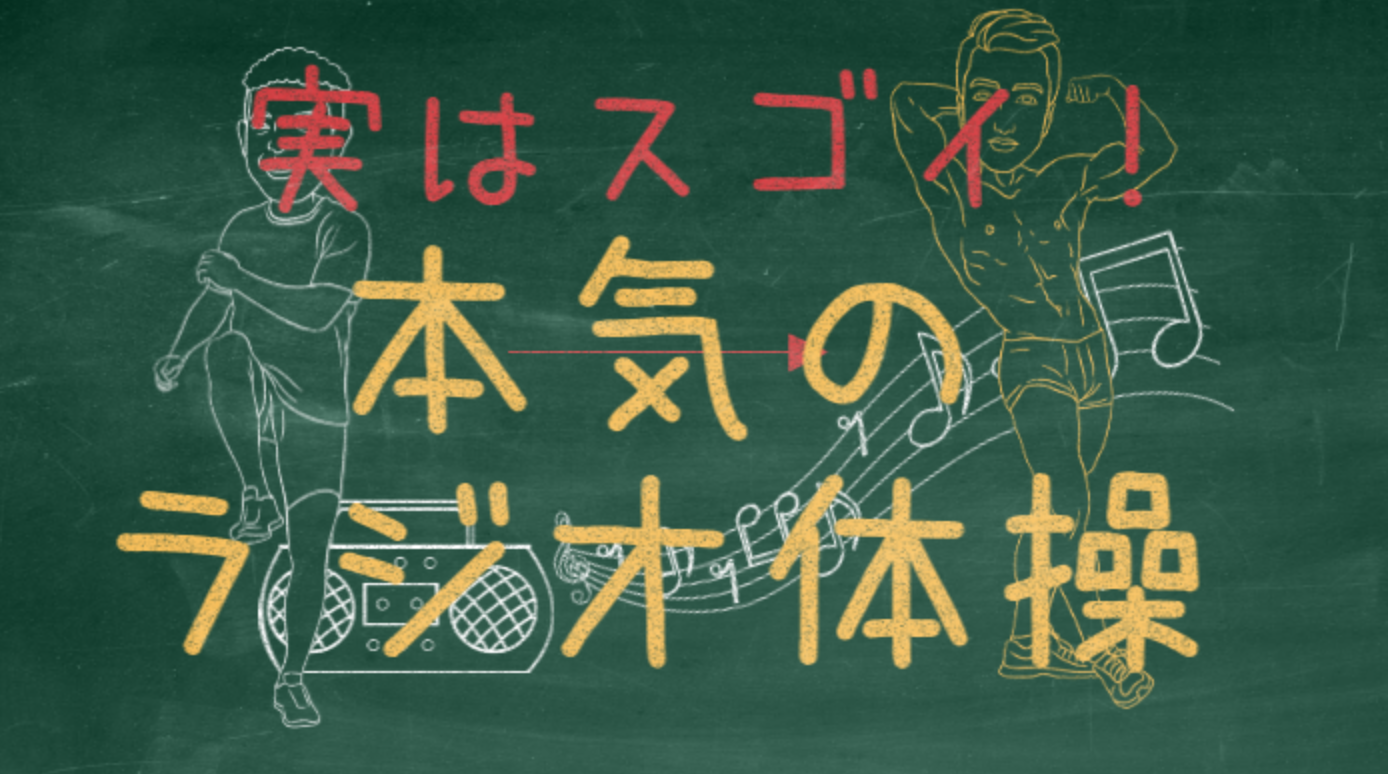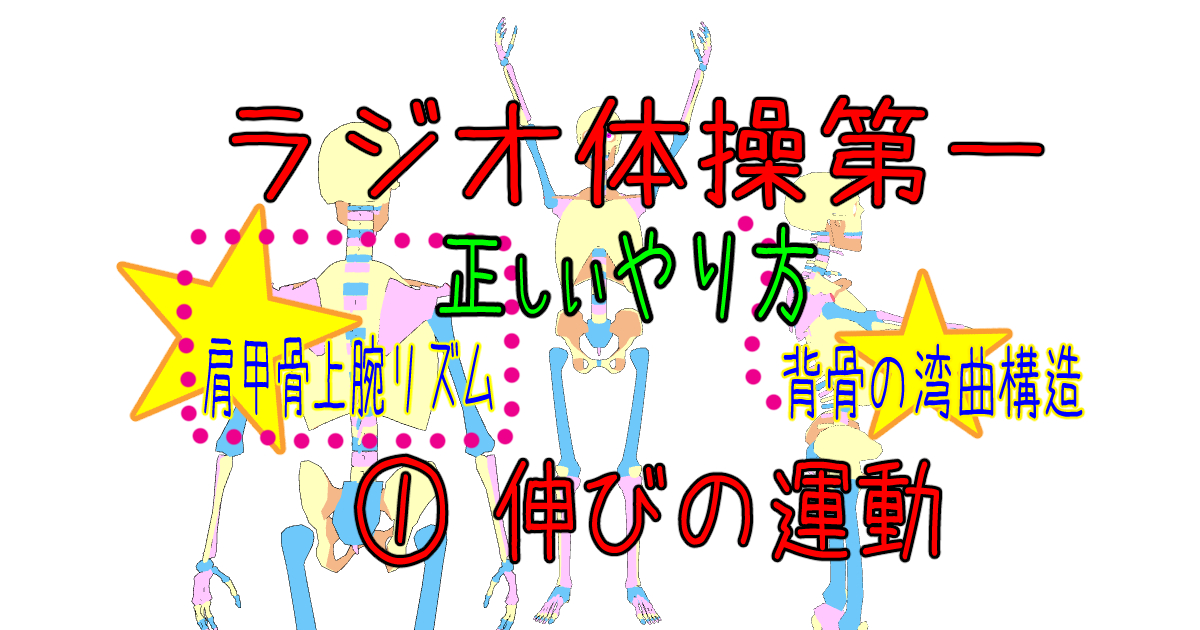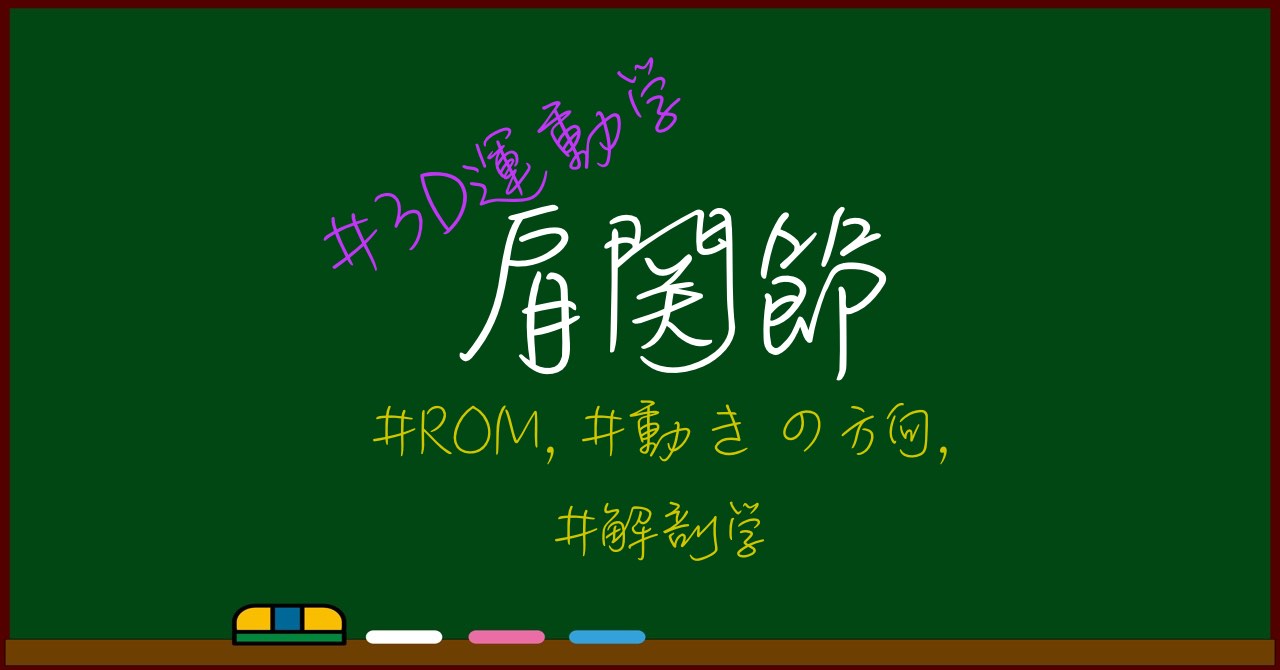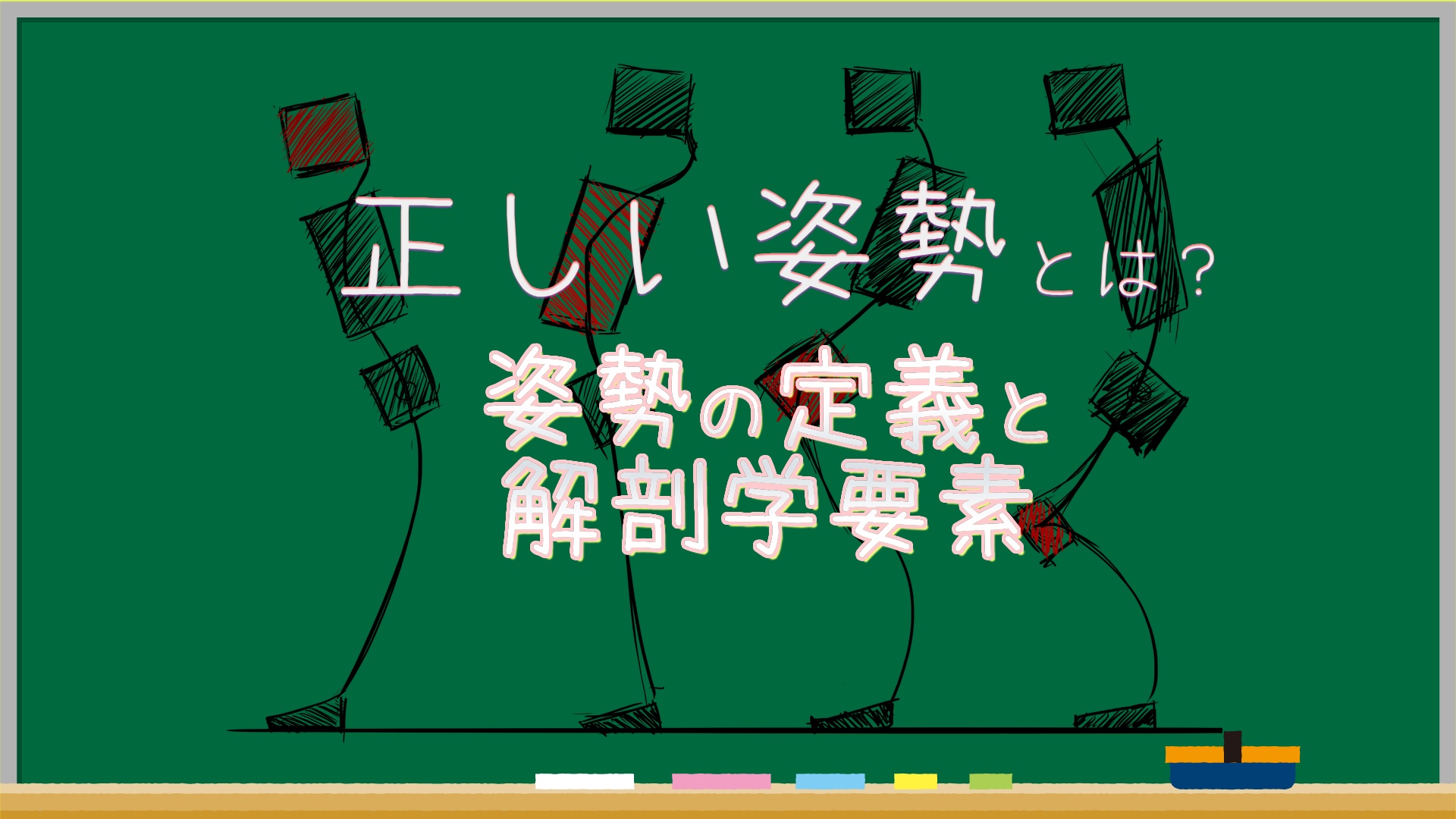たった3分で全身がととのう最強エクササイズ!「【ラジオ体操第二】③腕を前から開き回す運動」を解剖学と運動学の視点から分析し、うまくできない時の軽減方法やなりたいスタイルや目的に合わせたアレンジも提案します。
【ラジオ体操】3分で全身筋トレできる最強エクササイズ!
みんなやったことがあるけれど正しくできるいる人が意外に少ない「ラジオ体操」ですが、実はたった3分で全身をバランスよく整える美容健康効果に優れた最強エクササイズです。
【ラジオ体操第二】「老若男女を問わず誰でもできることにポイントを置いたラジオ体操第一」よりも運動負荷が大きく、体を鍛えて筋力を強化することをポイントにおいています。
面白いのが、同じ名前の体操でも【ラジオ体操第一】と【ラジオ体操第二】で動きや注目ポイントが異なるので、第一と第二を組み合わせると、更なる美容健康効果が期待できます。
みんなやったことがあるけれど正しくできるいる人が意外に少ない「ラジオ体操」ですが、実はたった3分で全身をバランスよく整える美容健康効果に優れた最強エクササイズです。
「ダイエットやボディメイクをしたいけれど何から始めたらよいかわからない」「運動を始めたいけど難しいのは続かない」なら、まず「ラジオ体操」を極めてみることをオススメします!
【③腕を前から開き回す運動】ラジオ体操の正しいやり方と解剖学
「【ラジオ体操第二】③腕を前から開き回す運動」は、「肩まわりの筋肉をほぐし柔軟性を高める」目的で作られ、以下の効果があると公式サイトでは記載されています。
公式サイトより引用
- 肩こり予防
- 柔軟性アップ
重要な運動要素
「【ラジオ体操第二】③腕を前から開き回す運動」は、肩関節(肩甲骨含む)を大きく動かす運動(ストレッチ)なので、肩こり、首こり、眼精疲労、頭痛などの原因になる猫背や背中が丸くなった不良姿勢改善に効果的です。
| 重要な運動 | 目的 |
|---|---|
| 肩関節運動 (全方向) | 可動域改善(柔軟性向上) 血流改善 姿勢改善 |
肩周りがほぐれることで血流も改善して自律神経バランスも整いやすくなるため、仕事や作業中にリフレッシュにも役立ちます。
準備姿勢(スタートポジション)
「【ラジオ体操第二】③腕を前から開き回す運動」の準備姿勢(スタートポジション)は、「【ラジオ体操第一】①伸びの運動」と同じ背骨と骨盤をニュートラルした良い姿勢を基準に、「前に倣え!」のように腕を肩の高さに上げた状態(肩関節屈曲90度)です。
運動方向と可動域
「【ラジオ体操第二】③腕を前から開き回す運動」では、2つの要素を4回繰り返すとなっていますが、肩関節(肩甲骨)を大きく動かすストレッチです。
公式サイトより引用
- 腕を水平に大きく開き、その反動で前に戻す
- 腕を振り下ろし前から後ろへまわす
| パーツ | 運動方向 |
|---|---|
| 姿勢軸 | 上方向へ引き上げて維持 |
| 肩関節 | 水平外転⇄水平内転 屈曲⇄伸展 |
「ラジオ体操効果を高めるコツ」と「よくある間違い(対処法)」
「【ラジオ体操第二】③腕を前から開き回す運動」のコツとして、公式サイトでは以下のように記載されていますが、腕をただ大きく回すというよりも、肩関節(肩甲骨含む)の運動方向と可動域を明確にすることで効果を最大限高められます。
肘をしっかりと伸ばして、腕は大きく動かしましょう
公式サイトより引用
もちろん、これまでの運動同様に、肩や首の余計な力を抜いて肩の関節の運動を正しく効果的に行うためには、正しい姿勢を作れていることが前提です。
| 運動要素 | 効果を高めるコツ |
|---|---|
| 姿勢軸 | 上方向へ伸ばしてニュートラルを維持 |
| 肩関節運動 | 運動方向と可動域を明確にする 体幹(上半身)との連動を意識する |
肩関節(上腕骨)運動が「肩甲骨」を介して上半身(胸郭)と連動することを意識して行うことで、肩こりや腕の上がりにくさの評価や体操の効果も実感しやすくなります。
肩関節の解剖学構造を意識する
「肩関節」は人体の中でも一番可動範囲が大きく関わる筋肉の数も多いため、姿勢や目線、筋肉の緊張状態によっても可動域が変わってきますので、肩関節の解剖学構造を理解していることで正しい運動方向がわかるようになります。
また、上腕骨の動きに連動して、肩甲骨と鎖骨の動きも関与してくる(肩甲上腕リズム)ので、肩甲骨の動きも意識することで可動域や運動の滑らかさにも違いが出ることを意識できるようになると更に効果を高められます。
自分の可動域(柔軟性)を見極める
反動(遠心力)を使って大きく肩関節を動かす意識を持つことで、短縮していたり、普段動きが少ない筋肉をストレッチする効果が高められますが、解剖学構造に沿って動かさないと遠心力で強い力がかかる分逆効果になった時のデメリットも大きいので、自分が動かしている関節の運動方向や可動域(作用している筋肉)を意識しながら行いましょう。
肩関節周りの筋肉が硬い場合や炎症や怪我などで肩関節運動に制限がある場合は、腕を上がる範囲までで止めておくか、ローテーターカフなどインナーマッスルを意識した小さな動きにしましょう。
姿勢が整い、肩周りの筋肉の柔軟性が向上すると自然と腕が上がりやすくなりますので、肩関節に作用する筋肉や筋膜のつながりまで意識することで、肩こりを予防改善するだけでなく、背面の筋肉の緊張を緩めて柔軟性向上効果や姿勢改善効果も高められます。
姿勢軸を維持する
肩や首の余計な力を抜いて腕を大きく肩関節可動域いっぱいに動かすには、安定した立位バランスが取れている必要がありますので、腕を動かす前に背骨と骨盤がニュートラルな良い姿勢が取れていることをしっかり意識しましょう。
通常「真っ直ぐ立った良い姿勢」では、足のつま先を真っ直ぐ前に揃えた状態ですが、公式サイトの正しいやり方の動画や図解では、かかとは左右揃えたままつま先を外に45度程度開いていますが、足のつま先位置は真っ直ぐに揃えたり、脚幅を少し開いた方が立位が安定します。
足を揃えたり、つま先を外に向けようとすると立位がグラグラしたり、骨盤が傾いて背筋が真っ直ぐにならない場合は、骨盤と背骨のニュートラルを最優先にして、つま先の向きや脚幅を調整しましょう。
自分の身体の軸がわかって体幹の筋力がついてくると、足を揃えたきれいな立位が自然ととれるようになってきますし、つま先を外に開いた公式の姿勢にも自然と挑戦できるようになります。