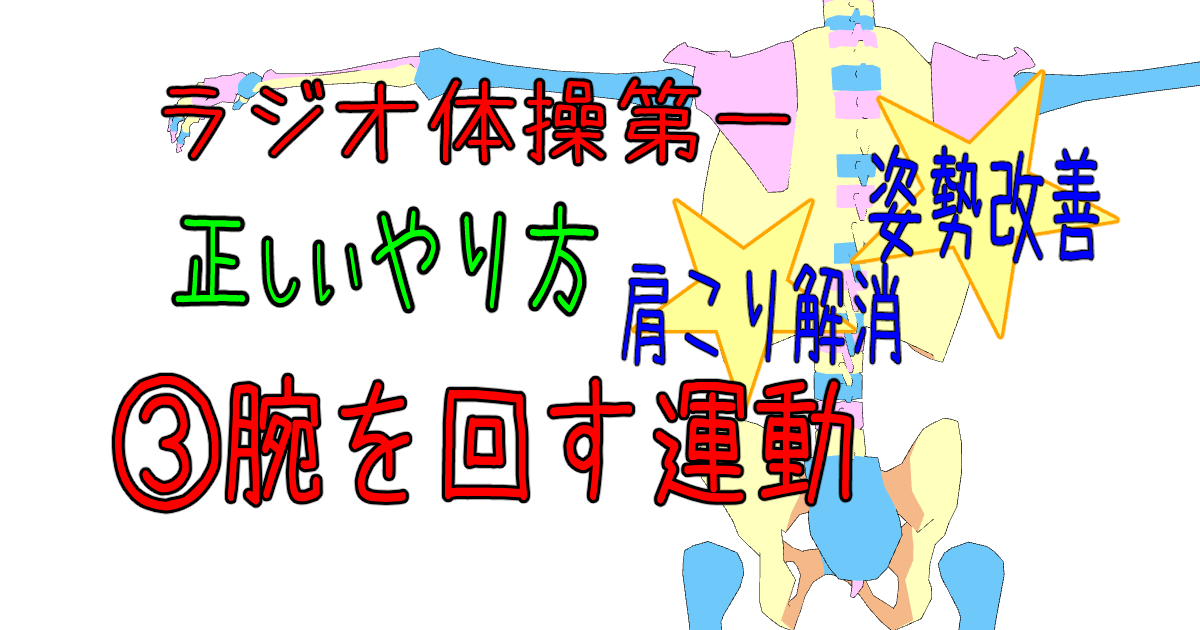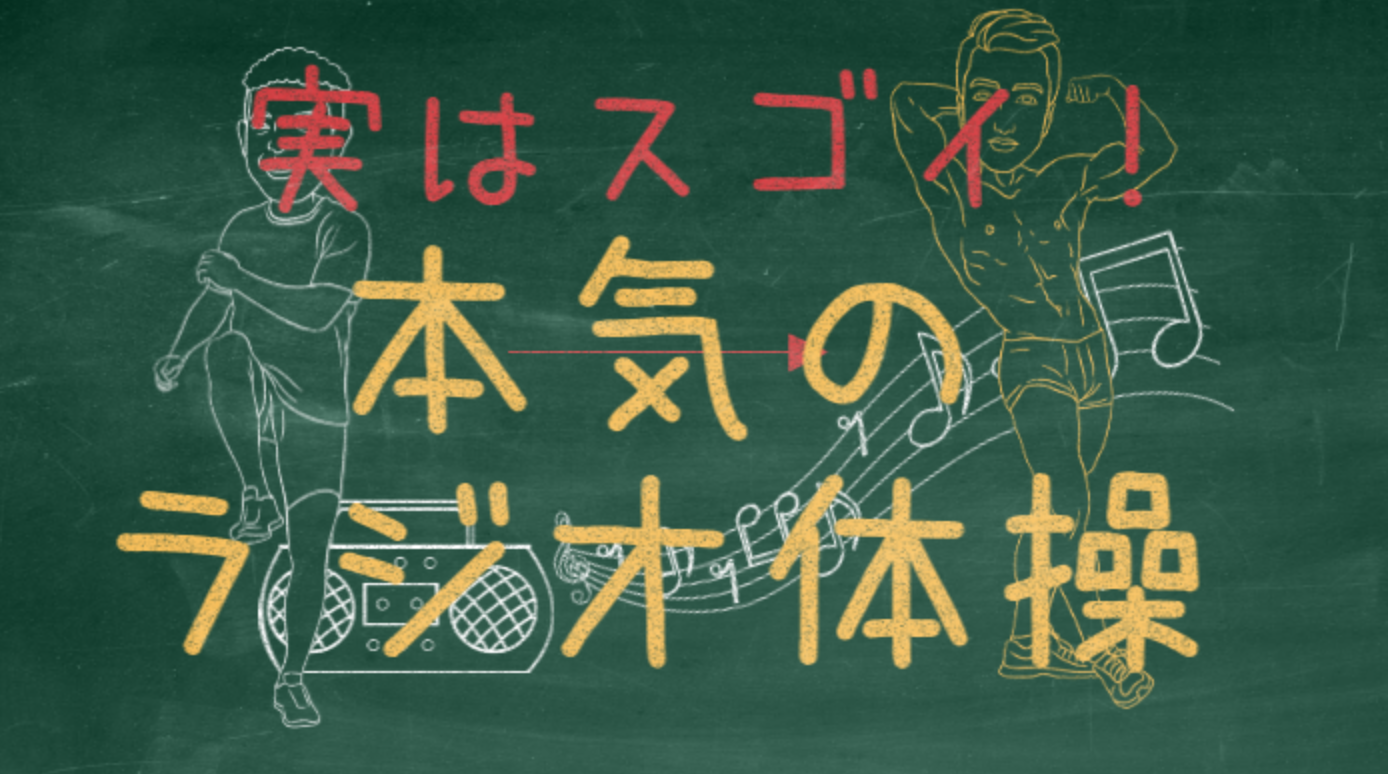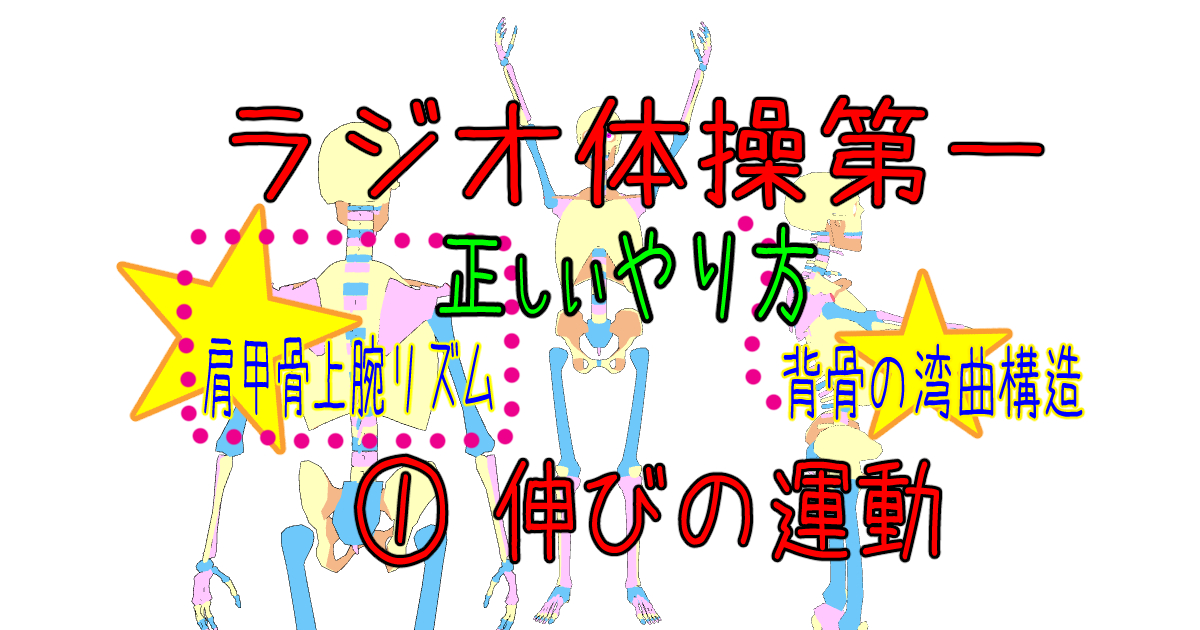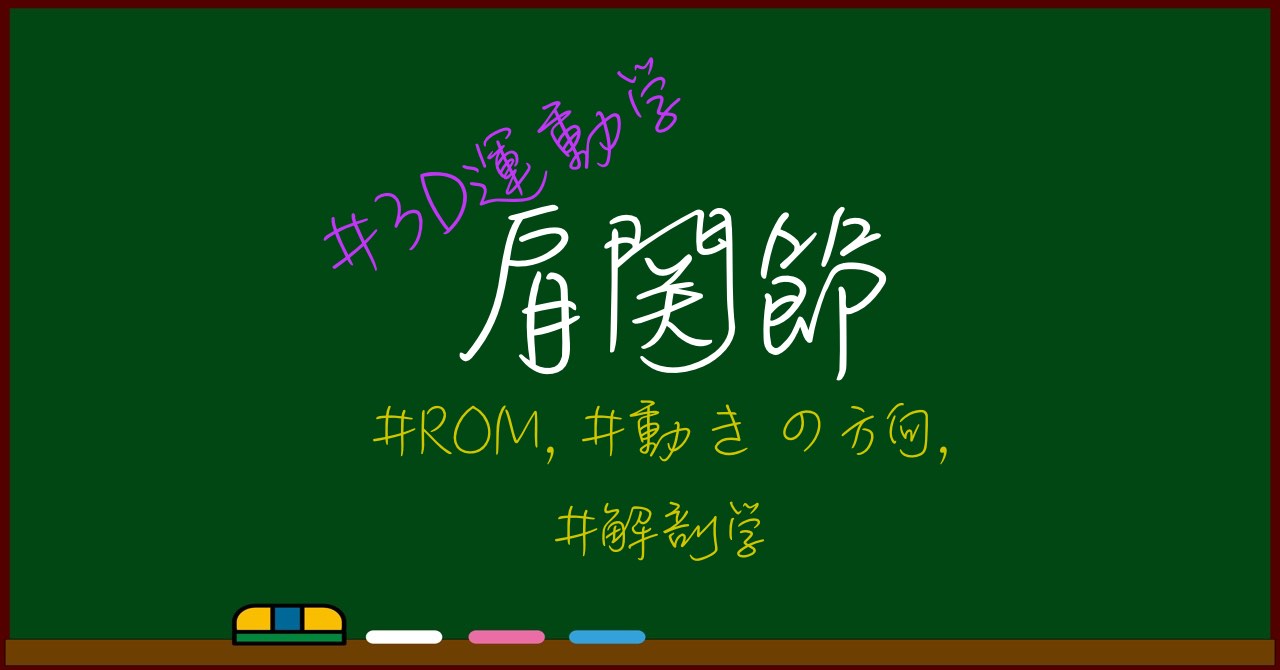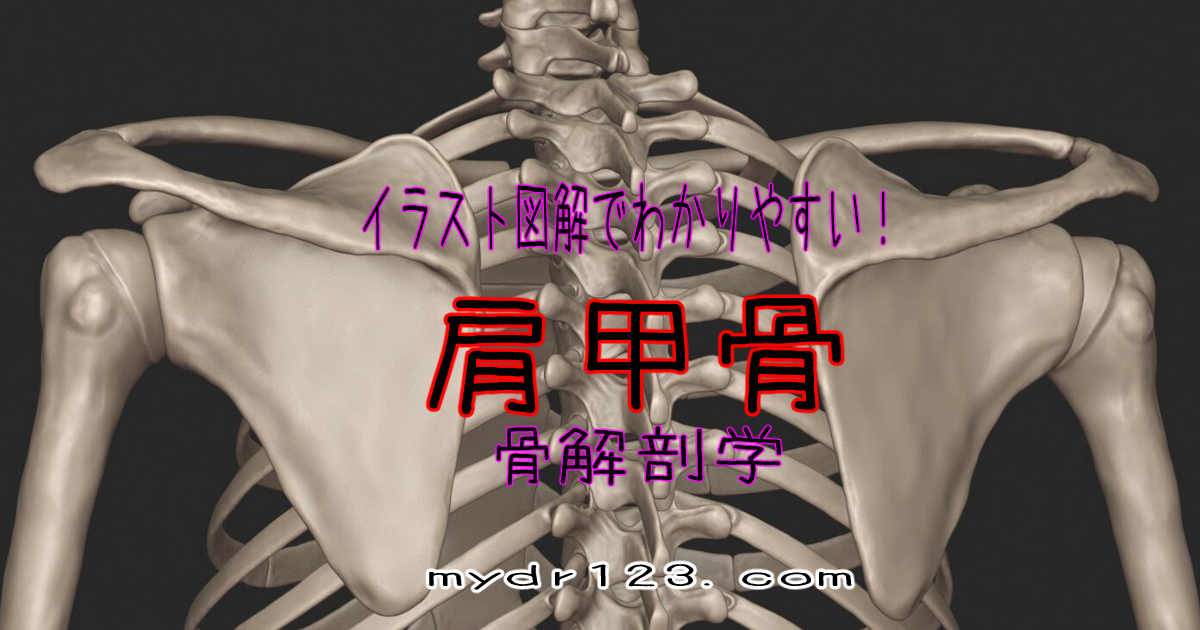たった3分!誰でもできる最強エクササイズ「【ラジオ体操第一】③腕を回す運動」を解剖学と運動学の視点から分析し、「うまくできない時の軽減方法」「効果を高めるためのコツ」「上級者向けアレンジ」などを提案します。
【ラジオ体操】は3分で終わる最強エクササイズ!
「なにか運動しないと!」と思ったらまず選択肢に入れて欲しいのが【ラジオ体操第1】!
わかりやすいシンプルな体操の組み合わせで老若男女誰でもできるように作られている体操なので軽い運動効果しかないと思っている人も多いのですが、【ラジオ体操】を正しく理解して丁寧に実践すれば、たった3分でも全身をバランスよく整える美容健康効果に優れた最強エクササイズになります。
「ダイエットやボディメイクをしたいけれど何から始めたらよいかわからない」「運動を始めたいけど難しいのは続かない」など身体の悩みがあるけれどどんな運動がいいかわからない場合は、まず「ラジオ体操」を極めてみることをオススメします!
【③腕を回す運動】ラジオ体操の正しいやり方と解剖学
ラジオ体操第一の3番目やるエクササイズは、【腕を回す運動】です。
「肩まわりの筋肉を柔軟に保つ」ことが目的で、公式サイトには以下のような効果があると記載されています。
【公式サイトより引用】
- 肩こり予防
- 血行促進
- 首の疲労回復
重要な運動要素
「【ラジオ体操第一】③腕を回す運動」でポイントになるのは「肩関節」で、肩関節の解剖学構造や運動学(運動方向や可動域)と上半身や姿勢に対する腕の動き(肩甲上腕リズム)を理解していると、正しい運動で高い肩関節柔軟性向上(可動域改善)効果が期待できます。
| 重要な運動 | 目的 |
|---|---|
| 「肩関節」を全方向へ動かす | 「肩関節」柔軟性向上(可動域改善) 姿勢と上肢運動の関係を意識する 循環改善 |
デスクワークやスマホの長時間使用で猫背や背中が丸くなった状態が続くと、肩こりや首こり、ひどくなると眼精疲労や頭痛にもつながってしまいます。
よい姿勢を維持しながら「肩関節(肩甲骨含む)」を大きく動かす運動を習慣化することで、肩こりの予防解消効果はもちろん、姿勢が整いやすく修正しやすくなるので、首から上のコリに関連する様々な体調不良や腰痛なども予防改善できますし、正しい方法をマスターすれば仕事や作業中にリフレッシュにも役立ちます。
基本姿勢(スタートポジション)
「【ラジオ体操第一】③腕を回す運動」の準備姿勢(スタートポジション)は、「【ラジオ体操第一】①伸びの運動」と同じ背骨と骨盤をニュートラルした良い姿勢から、腕を胸の前でクロスした(肩関節水平内転)状態です。
肩や首の余計な力を抜いて「肩関節」運動を正しく効果的に行うためには、「【ラジオ体操第一】①伸びの運動」で正しい姿勢を作れて維持できることが前提です。
運動方向と可動域
「【ラジオ体操第一】③腕を回す運動」のやり方やコツについて公式サイトでは以下のように記載されています。
腕や肩の力を抜き、遠心力を使って大きく回しましょう(4回繰り返す)
【公式サイトより引用】
- 腕を身体の外側から内側へ大きく回す
- 反対回し
人体最大の可動域を持つ球関節「肩関節」は4つの関節による複合体で、運動軸となる「上腕骨」に合わせて「肩甲骨」が動くなど、実際にはもっと複雑な運動ですが、わかりやすい粗大要素だけ抜き出して単純化しています。
| パーツ | 運動方向 |
|---|---|
| 肩関節 | 全方向 屈曲⇄伸展 内転⇄外転 水平外転⇄水平内転 円運動 |
「ラジオ体操効果を高めるコツ」と「よくある間違いの対処法」
「【ラジオ体操第一】③腕を回す運動」は、「肩関節」の解剖学構造や運動学、姿勢との相乗効果を意識することで効果を最大限高められます。
| 運動要素 | 効果を高めるコツ |
|---|---|
| 姿勢 | 上半身がリラックスできるように姿勢軸を安定させる |
| 肩関節 | 可動域と運動方向を意識する 上腕骨(腕)と肩甲骨(体幹)連携を意識する |
また、お手本通りの姿勢を作ろうとするよりも、その姿勢や動作をする目的を優先し、必要に応じて姿勢や運動方向の調整や軽減をしましょう。
肩まわりをリラックスさせる
「【ラジオ体操第一】③腕を回す運動」は「肩関節」を大きく最大可動域まで動かすダイナミックストレッチ要素がほとんどです。
「肩関節」運動には「肩甲骨」の動きも含むため、肩周りや上半身に余計な力が入って肩がすくんだり(耳と肩が近づく)しないように、身体の軸(背骨や骨盤)を安定させることが前提です。
首や肩に余計な力が入っていたり、スタートポジションが猫背や反り腰だったりすると正しい運動ができませんので、背骨と骨盤がニュートラルな良い姿勢が取れていることをしっかり意識しましょう。
肩関節の動き(可動域と運動方向)を正しく理解
肩関節は人体の中でも一番可動範囲が大きく関わる筋肉の数も多いため、姿勢や目線、筋肉の緊張状態によっても可動域が変わってきます。
「遠心力」を使って大きく肩関節を動かす意識を持つことで、短縮していたり、普段動きが少ない筋肉のストレッチ効果を高めることができますが、力強く大きな動きであればあるほど、遠心力で強い力がかかればかかるほど、間違った方向に動かして逆効果になった時のデメリットも大きくなってしまいます。
自分が動かしている関節の運動方向が正しいかどうか、自分の可動域の制限はどこにあるのかなど、肩関節の運動方向と可動域、腕と肩甲骨の動きの連動(肩甲上腕リズム)を意識しながら行いましょう。
肩関節の動きに制限やひっかかりを感じる場合は、無理に腕を大きく動かそうとすると身体の軸がぶれたり、腰を反ってしまったりする代償運動が出てしまい逆効果ですし、肩関節の解剖学構造が損傷して更に可動域が低下してしまう場合もあります。
姿勢が整い、肩周りの筋肉の柔軟性が向上すると自然と腕が上がりやすくなりますので、肩関節の柔軟性を高めるマッサージやストレッチなどを併用しながら少しづつ大きな動きにしていきましょう。
すでに、肩腱板断裂など肩に機能障害がある場合は、腕を下に垂らしたまま肩甲骨を動かしたり、肩甲骨やローテーターカフなどインナーマッスルを意識した小さな動きにしましょう。