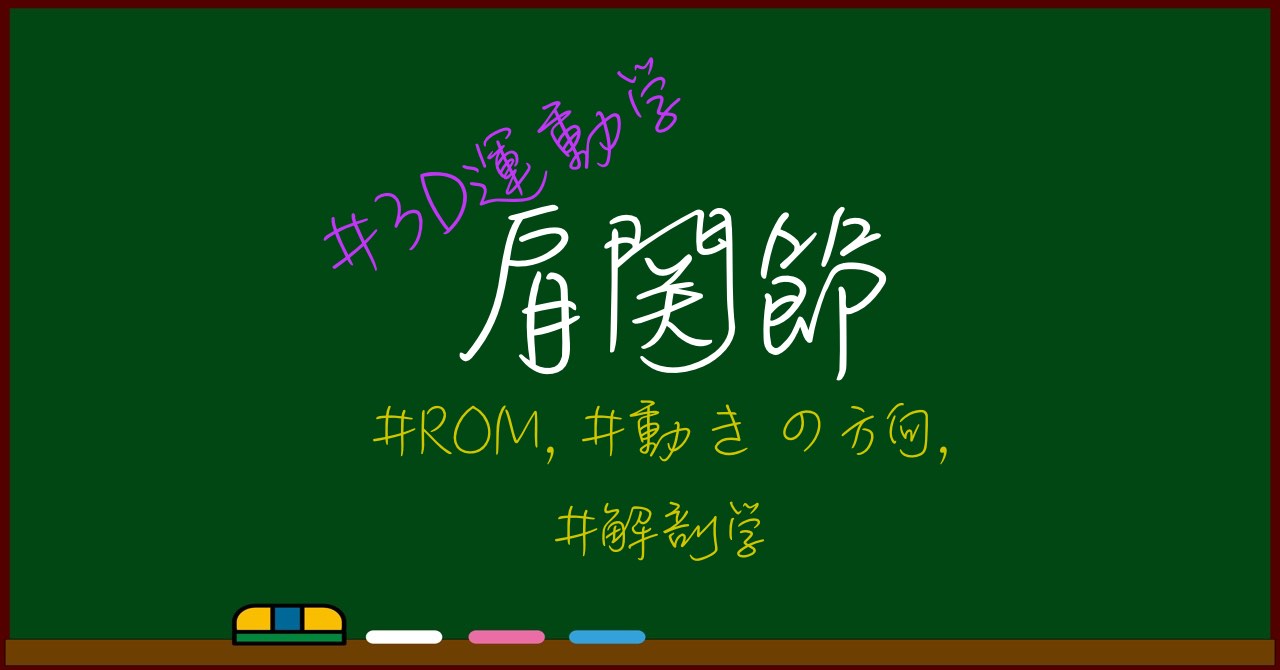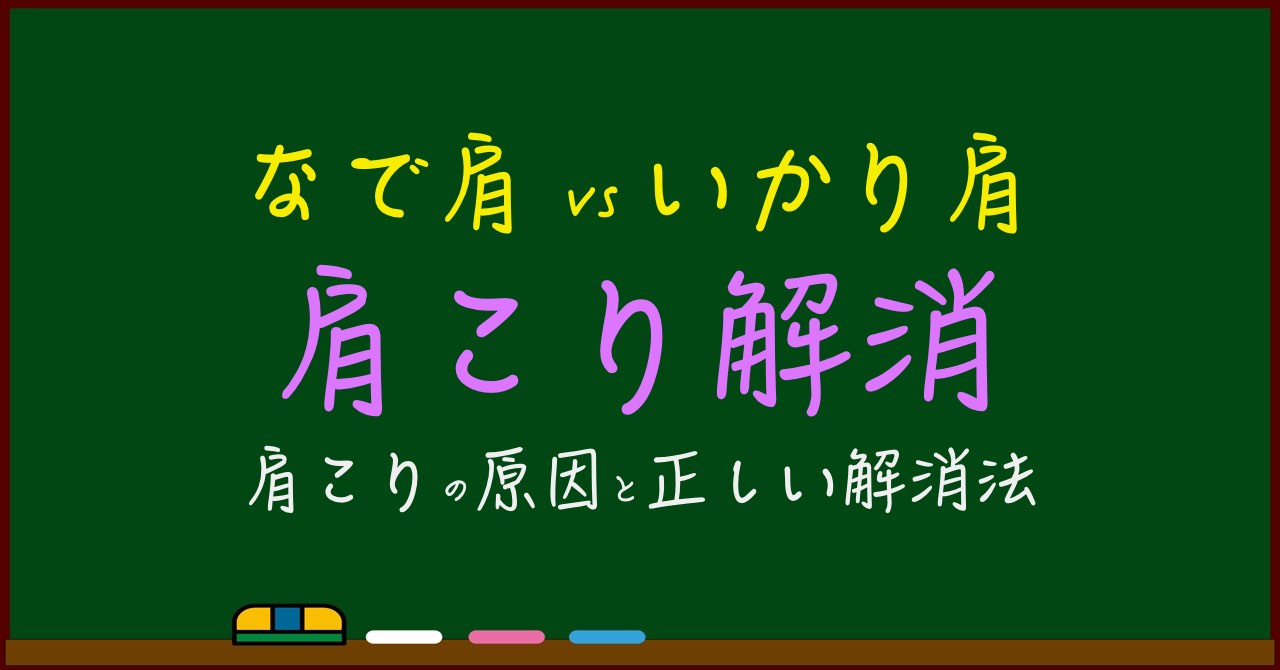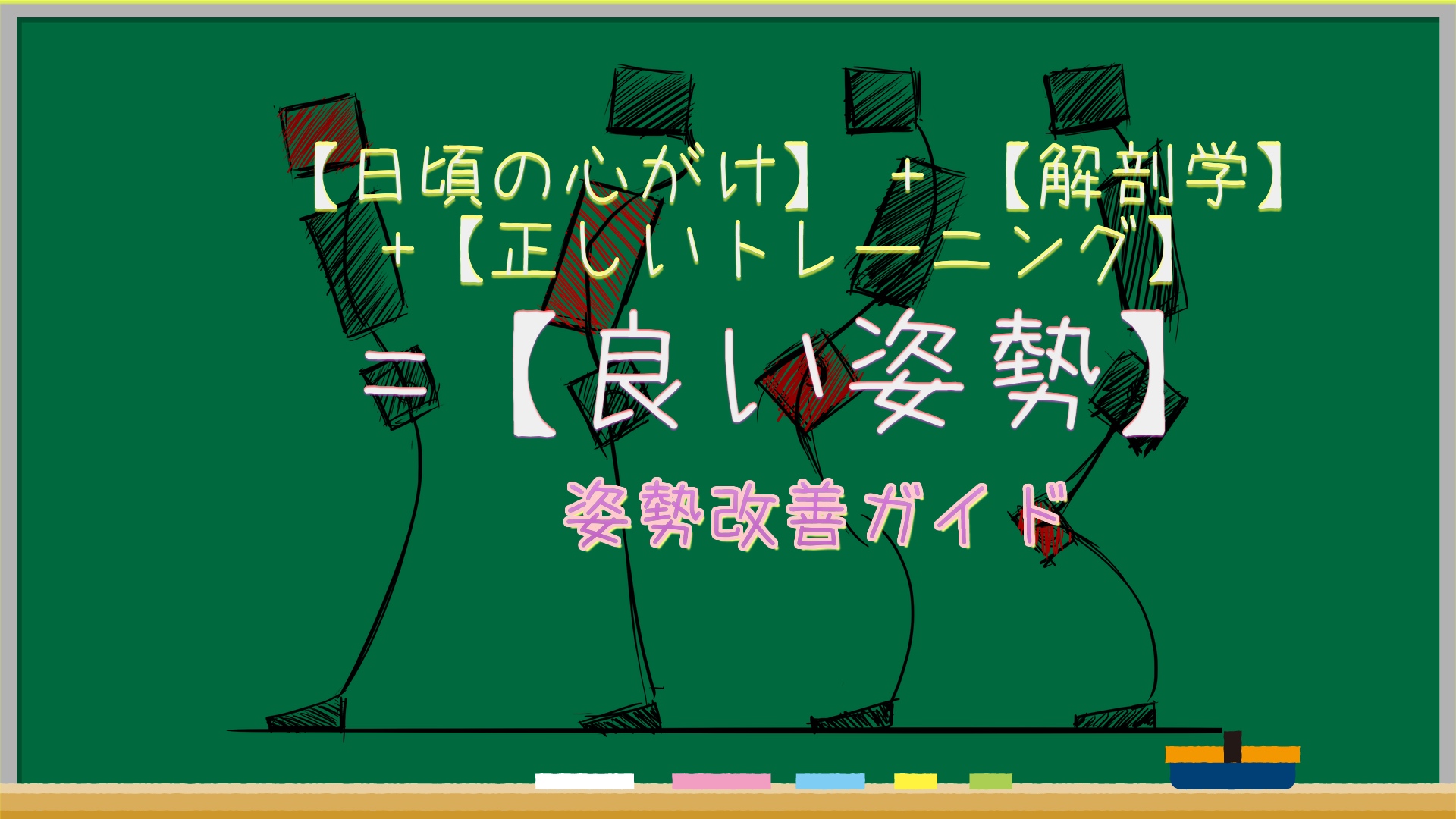40代〜50代で「腕が上がりにくい」とか「腕を動かすと痛みがある」などの症状があると「四十肩(五十肩)」と言われますが、その実態を知っていますか?
「四十肩(五十肩)」と年齢の関係や「肩こり」との関係、「肩の痛み」や「腕の上がりにくさ」など肩周りの問題を医学的に整理し、予防対策方法を丁寧に解説します。
【四十肩(五十肩)】とは何?
【四十肩(五十肩)】とは、「40代〜50代の肩こり」「腕の上がりにくさや腕を上げた時の痛みなど」を表現する名前として広く使われていますが、【四十肩(五十肩)】はギックリ腰などと同じ一般に使われる俗称です。
【四十肩(五十肩)】は「肩関節周囲炎」の俗称で、肩周りの筋肉・腱・靭帯のどこかまたは全部に炎症が起きている状態のことを言います。
40代〜50代で発症することが多いので【四十肩や五十肩】などと呼ばれるようになりましたが、特に年齢とは関係ありません。
つまり、「肩が痛い」「腕が上がらない」40代(50代)なら必ず【四十肩や五十肩(肩関節周囲炎)】という訳ではなく、40代未満でも四十肩や五十肩という俗称を持つ「肩関節周囲炎」になることはあります。
また、【四十肩(五十肩):「肩関節周囲炎」】と同じ様な可動域制限や痛みを伴う疾患には、「腱板断裂」「頸椎疾患」「神経の絞扼」などもあります。
肩の痛みや上がりにくさの原因を見極め、正しい対策が効果的にできるように、よくある肩周りトラブルの原因および傾向と対策をまとめました。
【肩周り(肩関節および肩甲骨)】解剖学構造
「肩が痛い」「腕が上がらない」など症状があった時、その原因は様々で、全てが【四十肩や五十肩(肩関節周囲炎)】と診断されるわけではありません。
肩周りの痛み、痺れ、動きにくさの原因を特定するためには、【肩関節】の解剖学構造の理解が不可欠です。
【肩関節】は腕を大きく広範囲動かす関節なので、その安定性と可動性を同時に維持するため、「肩甲骨」を介して体幹とつながっていることが注目すべき特徴であり、【肩周り】トラブルの原因を正確に特定するためには、腕を動かす動きに対する肩甲骨の動き(肩甲上腕リズム)も同時に整理する必要があります。
また、【肩関節】の主軸である肩甲上腕関節(上腕骨と肩甲骨で作る関節)は、骨結合が弱く、動きの大きい関節運動において、肩関節を安定させるために多数のインナーマッスルで補強されていますので、周囲の筋肉構造や役割も正しく理解する必要があります。
【四十肩(五十肩)】症状
「肩関節周囲炎」になると、【可動域制限(腕が上がらないなど)】と【痛みや痺れ】が生じ、日常生活でも様々な不便や辛さが生じます。
- 腕が上がらない(洗濯物干しや整髪ができない、など)
- 腕が回らない(洋服を着るときに苦労する、など)
- 肩周りが寝ていても痛い(首や腕にまで痛みが広がることも....)
肩関節の可動域が制限されると、様々な作業を行う手(指)が届く範囲が制限されるので日常生活がとても不便になります。
そして、一番辛いのが安静時でも続く痛みです。
症状が悪化すると、寝ているときなど特に肩関節に負担がかかっていなくも痛い状態になることもあり、腕や首まで痛くなってしまうこともあります。
【四十肩(五十肩)】原因:40〜50代で好発する理由
「肩関節周囲炎」は、肩周りの筋肉・腱・靭帯のどこかまたは全部に炎症が起きている状態なので、肩周りの筋肉・腱・靭帯に過剰な負担がかかっていて、十分な回復のためのケアがされてないことが原因です。
【肩関節】は、腕を重力に抗して常に身体にくっつけておく必要があるため、特に腕を大きく動かさないとしても肩周りの筋肉・腱・靭帯には、日頃からとても大きな負担がかかっています。
その上、ほとんどの人は髪をとかす、洗濯物をほす、棚の上の荷物を取るなど、日常生活で肩関節を重力や外力に抗する形で多用しています。
バレーボールのスパイクや野球のピッチングのような動作を含む活動やスポーツをする人なら、肩関節にはものすごい負荷がかかっています。
「肩関節周囲炎」が40代〜50代で起こりやすいのは、これまで肩関節にかけてきた負担が積もり積もって組織が耐えきれなくなって炎症として出てくるのがこの年代に多いということです。
もちろん、直接的に年齢は関係ないので、バレーのアタックなど肩に大きく使うスポーツする方、子供を長時間抱っこするお母さん、重い物を持つことが多い方などは若い年齢も「肩関節周囲炎」になることはあります。
人間の身体も様々なパーツを組み合わせてできた超精密機械のようなものなので、他の成人病や関節症などと一緒で、誤用や過用、負担が大きいと組織は壊れやすいということです。
【四十肩(五十肩)】の治療法
【四十肩(五十肩):「肩関節周囲炎」】は症状により炎症を抑える治療をしながら、痛みが治ったら可動域を改善するリハビリを実践する必要があります。
肩関節周りの組織(筋肉や靭帯)は複雑で動きのコントロールはとても難しく、また痛みのコントロール含めて長いスパンでみていく必要があります。
今すぐできる!【四十肩(五十肩)】予防対策
40代〜50代で起こりやすいと言われている【四十肩(五十肩):「肩関節周囲炎」】ですが、働き盛りのこの時期に、痛みや可動域制限で、長期的に活動制限されるのは大変です。
ただ、「肩関節周囲炎」は、「肩関節の負担(誤用や過用)を減らす」「正しいコンディショニングを継続する」ことで、ほぼ確実に予防ができる疾患でもあります。
40代〜50代だから肩が動きにくいのは仕方ないと言い訳せずに、肩関節の状態を良好に戻すコンディショニングを実践すれば、何歳からでも快適な肩関節や肩周りのコンディションを取り戻せます。
姿勢(猫背)や姿勢を直そう!
「猫背」などの不良姿勢は、肩甲骨が正常のアライメントになく、肩関節可動域も制限されて肩こりの原因にもなります。
この状態だけでも、肩関節周りの筋肉や靭帯の緊張にアンバランスが生じ、肩こりや腕の上がりにくさの原因になりますし、肩関節周囲の組織の誤用や過用が原因の【四十肩(五十肩):「肩関節周囲炎」】も生じやすくなってしまいます。
肩甲骨から肩関節を動かす意識を持とう!
「猫背」など姿勢が悪い場合は、ほぼ100%肩甲骨の可動域が低下していますので、この状態で腕を動かし続けることも「肩関節周囲炎」の原因になります。
【肩関節】の動きというと腕の動きばかりに意識が向きがちですが、実際の肩関節の動きは「肩甲骨を通じて体幹から生じていますので、肩関節の解剖学構造を意識し、肩甲骨(体幹)から腕を動かす意識を持つだけでも、肩関節周辺組織にかかる負担を軽減できます。
肩甲骨周辺組織をほぐして柔軟性を高めよう!
「肩甲骨ほぐし」というテクニックが流行していますが、肩甲骨周りを含め、凝りやすい背中の筋肉をほぐすメンテナンスを習慣づけることも、肩周りの負担軽減にとても有効です。
猫背だったり、肩が内巻きになっていたり、肩こりが慢性化していたり、スマホが手放せず、長時間のパソコン作業もさけられない現代の生活では、せめて寝る前にストレッチポールに乗って背中をほぐしたり、肩甲骨周りをほぐすストレッチやマッサージを実践し、その日の疲れやコリはその日の内にリセットすることで、肩への負担蓄積を予防しましょう!