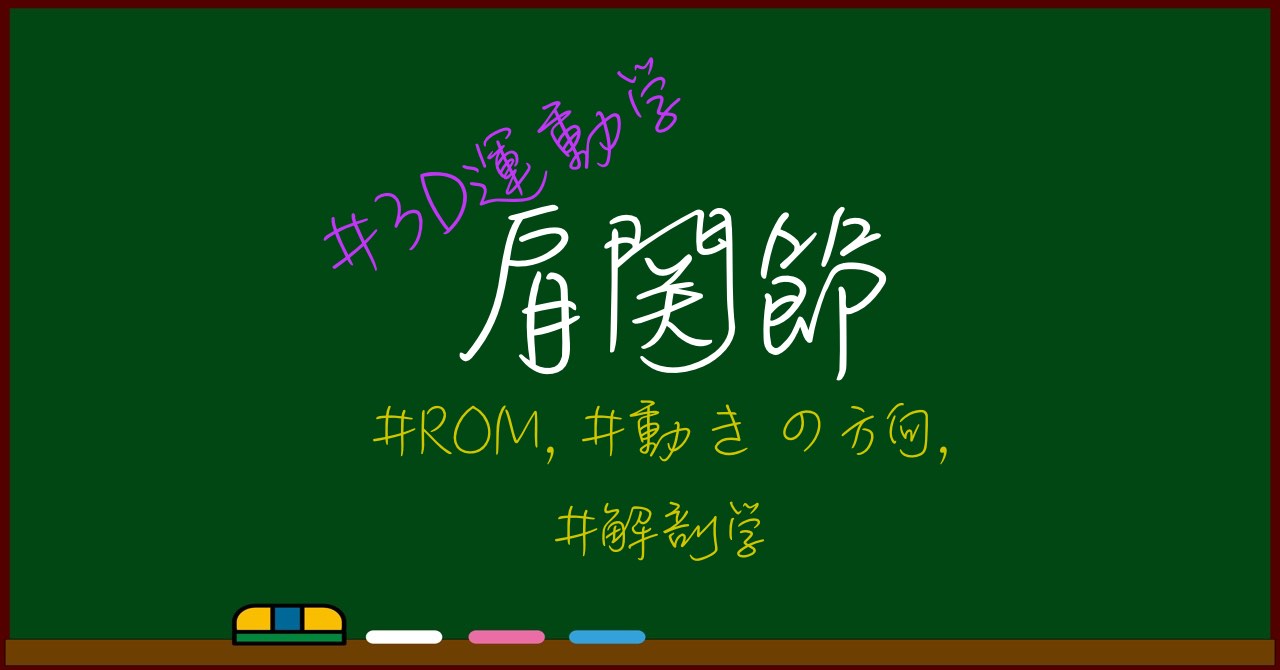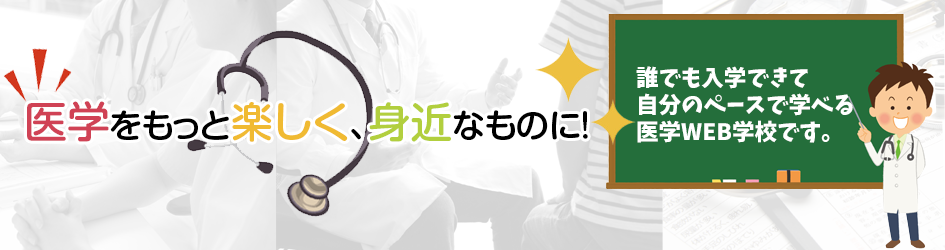骨と骨をつないで姿勢や運動軸を作る【関節】の解剖学構造や運動学(運動方向や可動域に関するメカニズム)について、イラスト図解を使ってわかりやすく整理しています。
【関節】とは?
【関節】とは骨と骨の間を繋ぐ(骨格を結びつける)構造で、姿勢や運動する時の身体のあり方(軸や運動方向)を決める主要要素で、可動域または結合組織構造により、それぞれ大きく3種類に分類できます。
人体には複数の骨と骨の結合である【関節】があり、「関節包」「筋肉(骨格筋)」「靭帯」などの組織にサポートされながら、運動や姿勢(ポジション)維持の軸となります。
【関節】種類:可動域による分類
【関節】は、可動域(運動範囲)によって以下の3種類に分類できます。
| 分類 | 構造と仕組み | 関節例 |
|---|---|---|
| 不動関節 | ほとんど動かない 安定を優先した関節 |
・頭蓋縫合線 ・歯と顎の結合 ・第一肋骨と胸骨の結合 |
| 半関節 | 単独では可動しない 他の関節運動と連動して限られた範囲で可動する関節 |
・恥骨(左右の恥骨)結合 ・下腿骨(脛骨と腓骨)間結合 ・前腕骨(橈骨と尺骨)間結合 |
| 可動関節 | 単独でも可動できる 運動を優先した関節 |
・股関節 ・肩関節 |
【関節】は臓器などを保護する空間を作ったり姿勢の軸となる安定の要素を作ると同時に、運動軸として特定の方向への可動性も有しています。
人体【関節】は、身体の部位(役割)ごとに結合する骨や軟部組織などによって可動範囲が異なる設計にすることで静と動のバランスをとっています。
【可動関節】
【可動関節】は、「股関節」や「肩関節」など運動する時に単独でも意識できる(わかりやすく動く)【関節】です。
【半関節】
【半関節】は、姿勢や他の「関節運動」に連動するように結合組織(繊維や軟骨)の可動範囲内で動く【関節】です。
「恥骨(左右の恥骨)結合」「下腿骨(脛骨と腓骨)間結合」「前腕骨(橈骨と尺骨)間結合」などが代表例です。
【不動関節】
【不動関節】は安定性を重視している構造で、「関節」ではなく「結合」や「線」などと呼ばれることもあります。
「頭蓋縫合線」「歯と顎の結合」「第一肋骨と胸骨の結合」など強固な骨結合が特徴です。
【関節】種類:構造による分類
【関節】は、「骨」と「骨」を結びつける解剖学的な組織構造の違いによって3種類(解剖学的関節) + 1種類(運動学的関節)に分類できます。
| 分類 | 構造と仕組み | 例 |
|---|---|---|
| 繊維性 (Fibrous) |
主に安定を目的とした関節構造 線や結合などと表現されることも多い |
・頭蓋骨の縫合線 ・歯と顎の関節 ・骨間膜結合 |
| 軟骨性(Cartilaginous) | 骨と軟骨が一体化した構造 特に中心部の安定性を維持しつつ重力を分散しつつ特定の方向へ動かす要素を持つ |
・第一肋骨と胸骨の関節 ・椎間関節 ・小児期の恥骨結合(成人は骨結合のみ) |
| 滑膜性 (Synovial) |
運動を起こす「可動関節」の代表的な構造 運動方向や可動域により更に6種類の構造に分類 |
・背骨や四肢の運動する全関節 |
| 機能性 | 運動学的に重要な「関節(骨構造同士の連携)」 解剖学上の関節構造はない |
・肩甲骨と胸郭による関節 (肩甲胸郭関節) |
姿勢を意識したり、運動やをする時に意識する【関節】のほとんどが【滑膜性関節】ですが、それぞれの関節構造(メカニズム)を正しく理解しておくことで、痛みや怪我を予防しつつ効果的な運動が行えるようになります。
【繊維性関節】構造と特徴
【繊維性関節】は、線維性結合組織によって構成される関節で、更に以下の3タイプ(種類)に分類できます。
| 分類 | 構造と仕組み | 可動性による分類 | 例 |
|---|---|---|---|
| 縫合線 (Suture joints) |
ジグザグの縫い目模様のような繊維で骨同士を結合 | 安定を目的とした「不動関節」 | ・頭蓋骨の縫合線 |
| 釘状関節 (Gomphosis joints) |
ペグがソケットにぴったりをはまる構造 | 安定を目的とした「不動関節」 | ・歯と上下顎骨による関節 |
| 靭帯結合 (Syndesmosis joints) |
「骨間膜」とも呼ばれる線維性結合組織で2つの骨間をつないだ構造 | 他の関節運動に連動して少ない可動範囲をもつ「半関節」 または「靭帯結合」 |
・前腕骨(橈骨と尺骨)間 ・下腿骨(脛骨と腓骨)間 |
【軟骨性関節】構造と特徴
【軟骨性関節】とは、「軟骨性」の結合組織で骨と骨を結合させている関節で、更に以下の2つに分類できます。
| 分類 | 構造と仕組み | 可動性による分類 | 例 |
|---|---|---|---|
| 軟骨結合 (Suture joints) |
骨と軟骨が一体化した構造 | 不動関節 | ・第一肋骨と胸骨の関節 |
| 繊維軟骨結合(Gomphosis joints) | 隣接する2つの骨の間に弾力性のある繊維軟骨性のパッドがクッションのように組み込まれている構造 | 安定性を維持しつつ重力を分散しながら特定の方向へ動かす機能あり 身体の中心軸を作る骨格(可動関節)に多い |
・「椎間板」で結合される椎間関節 ・小児期の恥骨結合(成人は骨結合のみ) |
【滑膜性関節】構造と特徴
【滑膜性関節】は結合する骨と骨の間に「関節包」があり、動くための関節である「可動関節」の代表的な構造です。
【滑膜性関節】は、骨結合(可動域)の特徴により更に以下の6つに分類でき、それぞれ特有の運動方向(特徴)があります。
| 分類 | 構造 | 動き特徴 | 代表例 |
|---|---|---|---|
| 球(きゅう)関節 (ball-and-socket) |
球形の骨端が他の骨のカップ(お皿)状のソケットに収まる構造 | 運動軸の制限がほとんどないため、滑膜関節の中でも最も可動範囲や方向に幅がある | ・肩関節 (肩甲窩と上腕骨骨頭) |
| 臼状(きゅうじょう)関節(ball-and-socket) | 球形の骨端が他の骨のカップ状のソケットに収まる構造 | 球関節同様に可動域は広いが、安定性はより高い | ・股関節 (大腿骨骨頭と寛骨臼) |
| 蝶番(ちょうつがい)関節(hinge) | 骨の凸面ともう一方の骨の凹面結合する構造 | ドアの開閉のように基本的に単軸方向の運動 骨構造により回旋や滑りなどの運動も同時に生じる場合もあり |
・肘関節 ・指関節 ・顎関節 ・膝関節(回旋や滑り含む) ・足関節(回旋や滑り含む) |
| 車軸(しゃじく)関節(pivot) | 丸い骨端がもう片方の骨または靭帯で構成されるリング状構造内 | 骨自体が軸となって回旋する | ・環椎軸椎関節(上位頸椎関節) ・橈尺関節(肘または手首) |
| 鞍(あん)関節 (saddle) |
サドル状の凹凸がある骨端同士が垂直方向で面して構成 | 可動域は蝶番関節よりもわずかに大きい | ・母指の手根中手関節 ・鎖骨内側と胸骨柄による胸鎖関節(SC) |
| 滑走(かっそう)関節 平面(へいめん)関節 (gliding/plane) |
平またはわずかに湾曲した面を互いに滑走するように動く構造 | 滑膜性関節の中では最も可動範囲が小さい ほとんどが複合関節内に存在 |
・手根間関節 ・足根間関節 ・手根中手関節 ・仙腸関節 ・肋椎関節 ・胸肋関節 ・肩鎖関節 |
| 顆状(かじょう)関節(ellipsoid/condyloid) | 楕円形の骨端(凸)が他の骨の楕円形の空洞(凹)に収まる構造 | 球関節と類似 楕円形のため可動範囲が球関節よりも小さい |
・頭頸部の結合(環椎後頭関節) ・手首(橈骨手根関節) ・中手指節関節 |
「関節包」とは【滑膜性関節】にのみ存在する組織構造で、【関節】の安定性と可動性を両立させる関節周囲組織全体を指します。
具体的には、【関節】の潤滑剤になる滑液を含む「滑膜」を構成して骨関節面を保護する「軟骨」や、関節外側を補強する「繊維性組織(主に靭帯や椎間板)」が含まれ、運動中の摩耗や損傷を最小限に抑えつつ安定性と可動性高められるようになっています。
解剖学構造を持たない【機能関節】
人体には解剖学構造では分類できないけれど、運動学的に重要な「関節(骨構造同士の連携)」があり、これらも運動を考える上では【関節】と捉える必要があります。
機能関節の代表例は、「肩甲骨と胸郭による関節(肩甲胸郭関節)」です。
「肩甲骨」と「胸郭背面」には靭帯など結合組織による結合も関節包もありませんが、「肩甲骨」および「胸郭」が他の関節が作る解剖学的関節に連動して動きます。
【関節】運動方向の定義
ほとんどの【関節】の運動方向は、「角度」「回旋」「円」「滑走(すべり)」で説明でき、実際の運動では複数の【関節】運動方向が同時に生じています。
| 分類 | 構造と仕組み | 例 |
|---|---|---|
| 角度 | 2つの骨で作る角度が変わる運動 | 屈曲⇄伸展 内転⇄外転 |
| 回旋 | 空間における骨の位置は同じで骨自体が軸となって回旋する運動 | 回内⇄回外 |
| 円 | 関節内の骨の一端がほぼ静止した状態でもう一端が円を描くように動く 円錐ができるような運動 |
指を回す 腕を回す |
| 滑走 | 骨の平面と平面が滑るように動く運動 | プロトラクション ⇄リトラクション 内転⇄外転 内反⇄外反 |
【関節】運動面の定義
【関節】運動方向を整理する上で共通言語になる基本姿勢と3つの運動面(軸)があり、運動面ごとに対になる(拮抗する)運動方向が定義されています。
| 分類 | 面の説明 | 運動例 |
|---|---|---|
| 矢上面 | 体を垂直方向に右と左に分割する面 | 背骨や四肢の左右運動 (内転⇄外転 ) |
| 前額面 | 体を垂直方向に前部と後部に分割する面 | 背骨の側屈や四肢の前後運動 (屈曲⇄伸展) |
| 水平面 | 体を水平方向に上部と下部に分割する面 | 回旋運動 (ひねり) |
基本姿勢
【関節】運動方向を定義する際の基本姿勢(ニュートラルボジション)は、「背骨」が自然な湾曲を保ち「骨盤」は左右対称の立位で、掌と顔は正面を向き、左右の足に均等に体重が乗っている状態と定義しています。
これらの面で運動方向を分割することで、実際は複数の面で複合的に行われる運動の理解がしやすくなります。
矢上面
「矢上面」とは、体を垂直方向に右と左に分割する面のことです。
前額面
「前額面 」とは、体を垂直方向に前部と後部に分割する面のことです。
水平面
「 水平面」とは、体を水平方向に上部と下部に分割する面のことです。
【人体の可動関節】まとめ
運動や姿勢保持の際に意識する必要がある、主要な可動関節の運動方向についてはこちらで詳しく説明しています。
【関節】をサポートする組織
骨と骨の結合である【関節】は様々な組織にサポートされていて、【関節】としての安定性や可動性を維持できます。
| 組織名 | 特徴 |
|---|---|
| 関節包 | 【滑膜性関節】にのみ存在する組織構造 「軟骨」「靭帯」「椎間板」などを含む |
| 軟骨 | 「滑膜」により骨の関節面を保護する繊維性の組織構造 潤滑剤になる滑液を含む |
| 椎間板 | 上下の椎骨間で関節間(環椎/軸椎関節を除く)を満たすゲル状の組織 |
| 靭帯 | 周囲の筋肉群と直列につながる繊維性の組織 あらゆる角度で関節を動的に安定させる(最大可動域を越えさせない) |
| 骨格筋 | 関節を保護したり、関節を構成する骨を動かす |
関節包
「関節包」とは、【滑膜性関節】にのみ存在する組織構造で、関節の安定性と可動性を両立させる関節周囲組織全体を指します。
具体的には、【関節】の潤滑剤になる滑液を含む「滑膜」、骨の関節面を保護する「軟骨」、関節外側を補強する「繊維性組織(主に靭帯)」などが含まれ、運動中の摩耗や損傷を最小限に抑えつつ安定性と可動性高められるようになっています。
軟骨
「軟骨」は、関節の潤滑剤になる滑液を含む「滑膜」により骨の関節面を保護する繊維性の組織構造です。
椎間板
「椎間板」は、上下の椎骨間で関節間(環椎/軸椎関節を除く)を満たしている、外周は繊維質で強度があり中心部はゲル状の組織です。
硬い椎骨の間に弾力のあるゼリードーナツ(中心にジャムがたっぷり入ったドーナツ)のような「椎間板」があることで、上下の椎骨同士がぶつからずに姿勢保持や運動時に「背骨」にかかる衝撃を吸収できるので、体重を支える軸を維持しつつ、多様な方向へ動く背骨の可動性と安定性を支えています。
靭帯
【靭帯】は繊維性の組織で、周囲の筋肉群と直列につながってあらゆる角度で関節を動的に安定させています。
【靭帯】は、最大可動域を超えて関節が動かないように保護する仕組みですが、筋肉(骨格筋)のように鍛えることができない消耗品なので、関節の仕組みや構造を理解し、関節に過度な負担をかけない姿勢や運動方法を普段から意識する必要があります。
例えば、日本人に多い「Swayback」と呼ばれる典型的な悪い姿勢(骨盤が前に出て、みぞおちが落ちて首が前に出る姿勢)は、「頸部の靭帯」「鼠径靭帯」「膝裏靭帯」「背骨の靭帯」など全身のあらゆる靭帯に頼った筋肉を収縮させていない)立位なので、非常に危険です。
そもそも人間は立位保持(静止)に適した構造になっていないので、関節構造を理解した上で「骨格筋」を適切に収縮させ、運動をしたり姿勢を変化させながら靱帯に過度な負担をかけない意識がとても重要です。
骨格筋
「骨格筋」は骨に付着して関節を動かす要素として注目されがちですが、関節を保護したり安定性を高めるためにも重要な役割を持っています。
バナナの皮と【関節】の共通点
身近なものに例えるとことで医学はずっと身近な知識になりますので、最後におまけ的なお話を。
人間の【関節】は骨の発生と当時に作られ、「軟骨」「靭帯」「関節包」などで補強されながら、「動き(可動性)」「固定」「動きの受容器」としての3つの役割があります。
また、重力に対抗して姿勢を保持しながら運動を行う私たちの【関節】は体重の数倍の負荷を受けていますが、80年以上の耐久性(耐摩耗性)を有する優れた軸受システムにもなっています。
この高い機能性と耐久を維持するために重要な要素になっているのが摩擦係数で、私たちの【関節】の摩擦係数は、0.003~0.02と非常に低い値になっています。
生体関節の極低摩擦・極低摩耗は、軟骨内の液相成分が荷重を支持し摩擦を低減する二相性潤滑などが階層的・協調的に機能することにより実現されていると考えられていて、生体関節のこの巧みな潤滑機構は、多モード適応潤滑機構(軟骨からの水分の滲み出しによる滲出潤滑・関節液中の吸着成分による境界潤滑・軟骨表層に存在するプロテオグリカン凝集体が形成するゲル膜による表面ゲル水和潤滑)と称されています。
要するに、滑る時の抵抗が極限まで小さくする仕組みができているから【関節】の寿命が長いということで、「関節がよく滑る仕組みは、バナナの皮が滑りやすいこと」と同じ仕組みなんだそうです。
バナナの皮で滑るなんてコントの中だけの話のようですが、これを学術的に研究してなんとイグノーベル賞(物理学賞)を授賞してしまった日本人がいます。
『イグノーベル賞』は、ユーモアで笑わせ、かつ考えさせる研究や業績に贈られる賞で、本家ノーベル賞とは財団も別ですが、ユーモアセンスがないと言われがちな日本人が2019年時点で13年連続で授賞しているというとても興味深い賞です。
北里大医療衛生学部の馬渕清資教授が率いる研究チームは、バナナの皮の内側にたくさんあるゲル状物質を含んだカプセルのような極小組織が、靴で踏まれた圧力でつぶれ、にじみ出た液体が潤滑効果を高めることを実験データから検証して発表しました。
ちなみに、北里大医療衛生学部の馬渕清資教授が率いる研究チームの本職は人工関節の潤滑などの研究で、関節のすべりの説明をする際に「バナナの皮ですべる」話を取り入れていたそうです。
「関節の軟骨による摩擦軽減の仕組みとバナナの皮の摩擦低減の仕組みには共通点があるのでは?」という発想から、実際に検証してみたら世界に認められました。
『イグノーベル賞』を受賞した研究が評価されたポイントは、「バナナの皮が滑りやすいのは自明のことだが、それを科学的に立証できた」こと。
数値が低いほど滑りやすいことを示す摩擦係数は、内側を下にしたバナナの皮の上からリノリウムの床材を踏んだ場合、床材を直接踏んだ時の6分の1だったということです。